上場廃止って何?社員や株主はどうなるの? 理由・背景・事例を解説
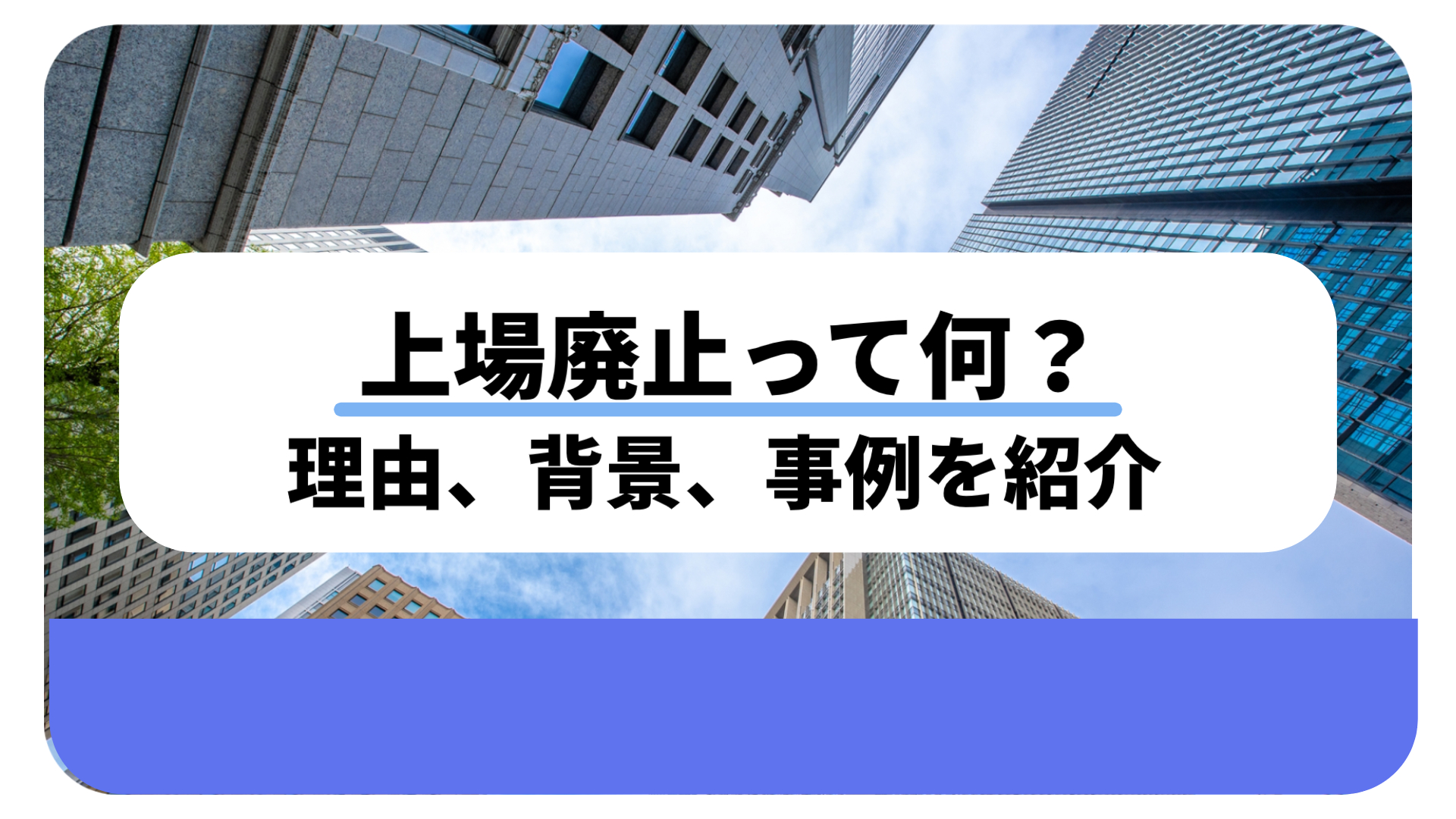
ニュースやインターネットで「上場廃止」という言葉を耳にしたこと人は多いのではないでしょうか。
実際には何が起きるのか、なぜ行われるのか、廃止後の社員や株主への影響はあるのか、などを正しく理解している人は少ないと思います。
本記事では、上場廃止の基本から、社員や株主への影響、企業が上場廃止を選ぶ理由と背景、実際に行った企業の事例までをわかりやすく解説していきます。
上場廃止とは?

「上場廃止」とは、株式市場に上場している企業の株式が、証券取引所で売買できなくなることを指します。
会社自体が無くなるわけではなく、市場での取引が終了し、株式が非公開化される状態です。
上場廃止になる原因は以下のものがあります。
- 上場廃止基準を下回った (例:経営不振や、開示違反による基準未達 など)
- 企業からの上場廃止申請 (例:MBOや、TOBによる非公開化 など)
ただし上場廃止には手続きや審査があるため、即日廃止になることはありません。
これらの原因は「上場廃止を行う理由」で解説しています。
上場廃止になると社員はどうなる?

上場廃止と聞くと「会社がなくなるのではないか」と不安を感じる方もいるかもしれません。
しかし、帝国データバンクの「上場企業倒産」動向調査(2024年)によれば、2024年に上場廃止となった94社のうち、実際に倒産に至ったのはわずか1社であり、上場廃止=倒産 というケースはごく稀です。
とはいえ、残る93社の中には、経営不振による子会社化や合併をした企業も含まれるため、こうしたケースでは社内環境に少なからず影響が及ぶ可能性があります。
待遇や雇用への影響
日本の法律では解雇は厳しく制限されているため、上場廃止を理由に社員をリストラすることはできません。
ただし、業績不振が深刻な場合には、経営再建の一環として整理解雇(リストラ)が行われることがあります。
また、上場企業は人的資本開示が義務化されており、従業員への投資や福利厚生を充実させる取り組みを行う企業も多く見られます。
そのため、上場廃止となった場合には、給与の削減や福利厚生の見直し、賞与カットなどが実施される可能性もあるため、上場廃止の背景により社員への影響は大きく異なります。
- 人的資本開示とは?
-
2023年3月期決算から、企業の人材育成方針・社内環境整備・多様性の状況などを開示する制度です。
人材育成方針、社内環境整備方針、従業員の状況(女性管理職比率、男女間賃金格差など)の開示が求められています。
引用元:金融庁「企業内容等の開示に関する内閣府令等改正の解説」
https://www.fsa.go.jp/news/r4/singi/20230523/01.pdf
従業員持株制度とストックオプション
従業員持株制度とは、社員の給与や賞与の一部を自社株に積み立てる仕組みで、安定的な資産形成につながります。
ストックオプションとは、あらかじめ決められた価格で自社株を取得できる権利であり、その価格より株価が上昇していれば社員が利益を得られる「インセンティブ報酬に近い」制度です。
しかし、上場廃止後は証券取引所で自由に売却できなくなるため、両制度とも換金性が低下してしまいます。
そのため、企業側が買い取りを行うケースもありますが、経営不振や倒産による廃止では大きく価値を落とし、社員の資産や報酬に大きな影響を与えるリスクがあります。
ローン審査への影響
金融機関が行う住宅ローンやマイカーローンでは、勤務先の安定性や信用力が重要になってきます。
上場企業は、安定した財政基盤や情報の透明性により、ローン審査で高い評価を受ける傾向にある反面、上場廃止の背景によっては会社の社会的信用が下がり、審査の評価に影響を及ぼす可能性があります。
株主への影響と動き

上場廃止は、株価に大きな影響を与えるため、発表から廃止に至るまでの流れを理解しておくことが重要です。
上場廃止発表
会社や取引所から上場廃止の発表がされ、理由や予定日、MBO・TOBの有無が公開されます。
- MBO・TOBとは?
-
MBOは経営陣が自社株を買い取り、上場廃止や経営権取得など行う行為です。
TOBはMBOを実現するために外部の第三者が株式を市場外で一括取得する手法のことです
市場価値より高い値段が提示されるため、株主にとっては売却の好機となります。
整理銘柄に指定
原則として廃止発表翌日に「整理銘柄」に指定され、約1ヶ月は市場での売買が可能になります。
市場での最後の取引機会になり、1ヵ月間株式の売買が行なわれた後、上場廃止となります。
上場廃止が決まった株はいつ売るべき?
- TOB型
-
提示された価格でTOBに応募するか、期間中に市場で売却するかを選ぶことになります。
TOBは市場価値より高い値段が提示されるため、株主にとっては売却の好機となります。廃止後は市場で売却できなくなり、強制買取や会社による株式交換が行われることもあります。
- 倒産型
-
倒産が発表されると市場はすぐに反応し、整理銘柄の株価は急落します。
期間中にも売買は可能ですが、株主にとって大きな損失になります。廃止後は、債権者への支払いを行うため、株主に配分されることはなく、株式は紙きれ同然になってしまいます。
上場廃止は、株主にとって資産価値や取引に直結する重要な出来事です。
TOBが行われる場合には、市場価格より高く売却できる可能性があり、株主に利益をもたらすケースもあります。
一方、倒産が背景にある企業では、株価は急落し、株主にとって大きな損失につながってしまいます。
※ このブログは創業22年のWeb企業「セルバ」が運営しています。
興味があれば[会社紹介はこちら]もご覧ください。
上場廃止になった株を持ち続けるとどうなる?

上場廃止後も株式を保有することはできます。具体的には以下の3つのパターンがあります。
スクイーズアウト(強制買取)
スクイーズアウトとは、少数の株主に対して、金銭等を交付して、強制的に株式を買い取る仕組みです。
スクイーズアウトには以下のような手法があります。
| 手法 | 持株比率 | 手法の内容 | |
|---|---|---|---|
| 株式等売渡請求 | 90%以上で実施可能 | 株式を90%以上保有した場合、残りを強制的に買い取ることができる制度 | |
| 全部取得条項付種類株式 | 50%以上で実施可能 | 会社があらかじめ株式の一括取得に関する条件を定めことができる制度 | |
| 株式交換 | 50%以上で実施可能 | 現金や親会社の株式を交付し、株式を取得する方法 | |
| 株式併合 | 持ち株制限なし | 株式を併合することで、少数の株式を1未満にする方法 (持ち株が1未満になると株主としての権利を行使できなくなるため、請求に対しての拒否権が無くなる) | |
すべての手法が無条件で行えるわけではなく、保有している株式により手法に違いがあります。
株式受渡請求には株主総会が不要で、最も強制力が強く、最短で行うことができます。
しかし、他の手法(全部取得条項付種類株式、株式交換、株式併合)では株主総会で3分の2以上の賛成が必要なため、持株比率の条件を達成していても実施できない場合もあります。
保有継続
上場廃止後も、会社が倒産や清算、買取を行わない限り株式を保有し続けることができます。
営業を続けている場合は、株主としての権利を行使できるため、配当を受け取れることもあります。
しかし、市場での自由な取引ができなくなるため、換金性は大きく低下します。
また、非上場企業の多くは株式の譲渡に制限を設けているため、売買をする際には、会社の承認が必要になります。
一方で、再上場や、親会社やファンドからの高値買取が行われる場合もあり、株式の価値が再び上昇する可能性もあります。
紙切れになる(無価値になる)
会社の倒産や清算が行われる場合には、会社の所有権である株式は法的に消滅します。
株式は会社にとって「資産」であり「負債」ではないため、会社は株主に対して返済する義務を負いません。
そのため、会社が破産手続きを行う際には、債権者への支払いが優先され、株主に分配が行われることはほとんどありません。
しかし、株式の損失は「譲渡損失」にあたるため、課税される範囲が変わってきます。
- A社で100万円の利益が出ていたが、B社が倒産したため株式が無価値になり30万円の損失が出た。
- A社の利益100万円から、B社の損失30万円を差し引いた70万円が課税対象。
- A社で100万円の利益が出ていたが、B社の株式を安い価格で売ったため30万円の損失が出た。
- A社の利益100万円から、B社の損失30万円を差し引いた70万円が課税対象。
倒産により損失を負った場合と、株式を安く売って損した場合でも課税範囲に違いはありません。
しかし、損失が確定するタイミングと手続きに違いがあります。
安く売って損した場合には、売却したタイミングで損失が確定し、証券会社で自動的に計算されます。
一方で、無価値による損失の場合には、破産手続開始決定が出た、特別清算開始命令が出た、清算結了登記が完了したなど、客観的に会社が再生不能と判断された時点で損失が確定します。
また、こうした損失は自動計算されないため、確定申告で損失を計上する必要があります。
上場廃止を行う理由
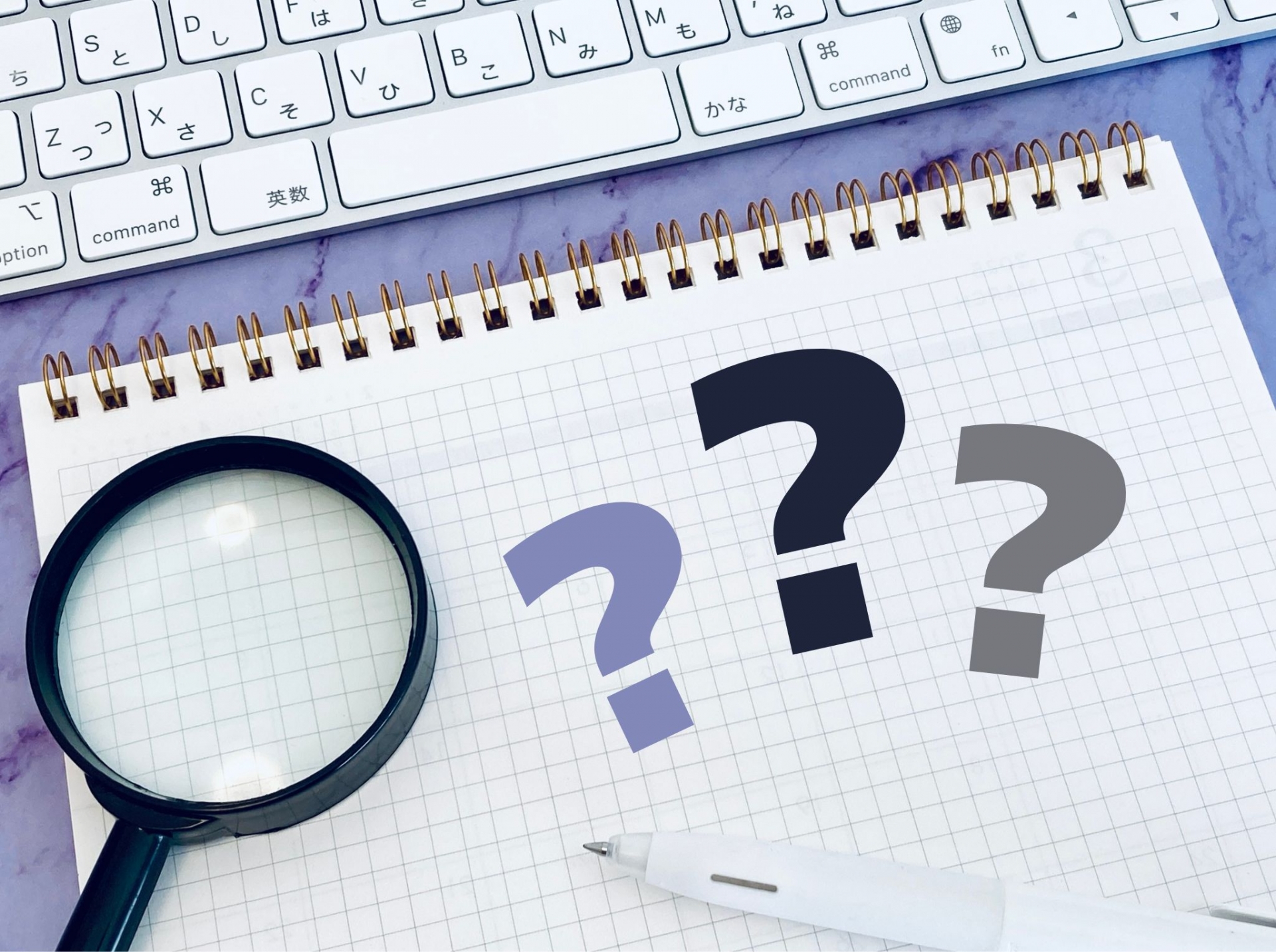
上場廃止は、倒産や経営不振だけでなく、経営戦略の一環として行われる場合もあります。
ここでは、そんな上場廃止を行う理由についてご紹介します。
戦略的要因
上場廃止には、企業が自ら選択して非公開を行う「戦略的要因」が存在します。
これは株式や市場を気にせずに、中長期的な経営判断やグループ戦略を行う目的で実行されています。
- MBO・TOBによる上場廃止
- 上場廃止を行うことで、株主からの圧力をなくし、迅速な意思決定と長期的な経営に専念する
- 完全子会社化
- 親会社が株式をすべて取得し、子会社化によるグループ一体経営を目的とする
- コスト削減
- 上場を維持するための開示、監査コストを回避する目的
- 経験の安定化
- 外部からの株式買い付けによって行う、経営権の奪取を避けるために、上場廃止し、買収を防ぐ
実際には、これらの要因が単独で作用するよりも、複数の要因が重なり上場廃止に至るケースが多いです。
倒産で上場廃止となるのは全体のごく一部であり、ほとんどは戦略的判断による非公開化や再編が理由です。
消極的要因(上場廃止基準)
企業が自ら選択して非公開化に進む「戦略的要因」もあれば、上場廃止基準を下回った「消極的要因」もあります。
以下が、日本取引所グループ発表している「上場廃止基準」です。
| 基準項目 | 上場廃止基準 | |||
|---|---|---|---|---|
| 上場維持基準への不適合 | 財務状況、時価総額の低下、株主数・流通株式数不足 など | |||
| 有価証券報告書等の提出遅延 | 監査報告書、有価証券報告書、半期報告書の提出遅延 | |||
| 虚偽記載又は不適正意見等 | 有価証券報告書等への虚偽の記載 | |||
| 特別注意銘柄等 | 会社の財務・経営・内部管理体制などの重大な不備 | |||
| 上場契約違反等 | 取引所との上場契約違反や、合併・破産による契約当事者の消滅 | |||
| その他 | 銀行取引の停止、破産手続、完全子会社化、反社会的勢力の関与 など | |||
上場廃止基準は、市場の健全性や投資家の保護を行うために設けられています。
これらの基準に抵触した場足、企業は市場に上場し続けることができなくなります。
ただし、直ちに上場廃止になるとは限らず、改善期間を設けるケースもあります。
基準違反による上場廃止もかなりの少数派であり、多くの企業は戦略的要因により上場廃止を行っています。
メリットとデメリット

上場廃止と聞くと、ネガティブな印象を抱く人も多いと思います。
しかし、上場廃止はデメリットだけでなく、企業に対して大きなメリットも存在します。
上場廃止のメリット
経営の自由度が高まる
上場廃止を行う最大の理由は、経営の自由度にあります。
上場企業は株主や市場、決算報告に対応するため、短期的な利益向上の圧力がかかります。
そのため、一時的な経営悪化を伴う経営改革や、中長期的な研究・開発投資などは、株主からの反発を招くことも少なくありません。
しかし、上場廃止を行うことで、株主構成を整理し、自由で迅速な意思決定を実現することができます。
上場維持コストの削減
上場を維持するためには、年間の上場料、開示書類の作成費用、弁護士や監査法人への報酬など、さまざまなコストが発生します。
会社の規模や市場によって金額は異なりますが、年間で数千万円から、なかには数億円規模の費用がかかる企業もあります。
上場廃止後はこうしたコストを大幅に削減でき、事業や人材への投資などを行うことができます。
経営権の安定化
上場企業では株式が自由に取引されているため、株を集めれば誰でも経営に影響を与えることができます。
この仕組みは、市場の流動性や資金調達のしやすさといったメリットがある一方で、敵対的買収や意図しない株主構成の変化といったリスクも伴います。
上場廃止を行うことで、株式の自由な取引を制限し、経営権の安定化を図ることが可能になります。
また、上場企業では取締役の任期が原則2年以内と定められていますが、非公開化した企業では最長10年まで延長できるため、任期更新の手間やコストを削減し、長期的な経営方針を維持しやすくなります。
上場廃止のデメリット
資金調達が難しくなる
上場廃止を行う最大の理由は、株式市場からの資金調達にあります。
株式を新規発行することで、短期間で多額の資金を集めることができます。
銀行融資とは異なり、投資家が会社に「出資」する仕組みであり、投資家は出資の代わりに、配当や議決権などを得ますが、会社はその資金を返済する義務を負いません。
そのため、株式は「借入金」ではなく、「資本」として扱われるため、財務上の負債になりません。
しかし、上場廃止を行うことで、市場を通じた資金調達の手段は失われます。
資金調達は銀行融資や投資会社、親会社など限られた手段に依存せざるを得なくなります。
銀行融資は返済義務があり、利息や担保の設定が求められるため、財務の柔軟性が低下してしまいます。
知名度と社会的信用の低下
上場企業は、厳格な審査と、継続的な監査を受けることから、社会的信用の象徴といえます。
そのため、市場や取引先、金融機関から高い評価を得やすく、経営の透明性が信頼の根拠となっています。
しかし、上場廃止を行うことで、「信頼の保証」を失うことになります。
株式市場での評価(株価)がなくなることで、企業価値を示す指標が失われ、金融機関からの信用力も下がり、資金調達はさらに難しくなります。
また、非上場化により株主や投資家の関心が薄れ、メディアや投資家向けサイトなどで取り上げられる機会も減少し、知名度の低下につながってしまいます。
「上場企業」というステータスは企業ブランドの一部でもあり、それを失うことで、採用市場や取引先からの印象が弱まる可能性もあります。
上場廃止した有名企業とその目的

上場廃止と聞くと、経営危機や倒産を想像する人も多いかもしれません。
しかし先述の通り、上場廃止した企業の多くは経営改革や長期戦略を目的としています。
ここでは、上場廃止を行った有名企業の事例をもとに、廃止を行った背景をご紹介します。
東芝
東芝は、1949年に上場した日本を代表する電機メーカーです。
上場廃止に至った要因は、経営陣と株主の対立にあります。
買収した原発事業が大幅なコスト超過と遅延を招き、東芝は1兆円を超える損失を計上し、債務超過に陥りました。
債務超過に対応するため、東芝は海外投資ファンド60社を引受先とする6,000億円の増資を実施しました。
しかし、この投資ファンドの中には、短期的な利益を追求する企業や、業績向上を強く迫る企業も含まれており、長期的な再建を目指す経営陣との間で深刻な対立が生じました。
この状況を打破するために2023年に、国内投信ファンドの日本産業パートナーズなどの企業連合がTOB(公開買い付け)を実施し、同年12月に上場を廃止しました。
現在の東芝は経営再建の途上にあり、「上場廃止=倒産」ではなく、経営改革を進めるための戦略といえます。
ファミリーマート(伊藤忠商事)
ファミリーマートは、1987年に上場した日本を代表するコンビニエンスストアチェーンです。
2020年に、親会社である伊藤忠商事がファミリーマートをTOB(公開買い付け)を経て、上場を廃止しました。
その背景には、グループ経営の効率化と経営資源の最適活用があります。
伊藤忠グループの物流網やデジタル戦略といった強みを最大限に生かし、低コストで効率的な経営を行うことを目的として上場廃止が行われました。
非公開化後は、独自アプリの開発やインバウンド需要の取り込み、アパレル商品の展開など、経営資源を活かした新たな取り組みを進めています。
その結果、業績は大きく伸び、2025年2月期の営業利益は約850億円を記録し、過去最高益となりました。
まとめ
上場廃止は、単なる経営不振や倒産ではなく、経営戦略を目的とした場合がほとんどです。
社員にとっては雇用や待遇、株主にとっては資産や取引に影響はありますが、経営の自由度を高め、成長をするために企業は上場廃止を行っています。
上場廃止は決して会社の終わりではなく、経営改革を進めるための戦略のひとつといえます。
マーケティングや経営の考え方は時代や市場によって常に変化します。
今回ご紹介した内容も、一つの視点として参考にしていただければ幸いです。
気になるテーマがあれば、関連するコラムもあわせてご覧ください。


