コンサルは廃業が多い!?それでもITコンサルを目指すべき理由


自由に働けて高収入なコンサルに憧れる



自分の強みを活かして世の中に貢献する仕事がしたい
コンサル業に対して、そんなイメージを抱く人も多いと思います。
特に近年は、独立してコンサル業を始める人が増えていますが、その一方で、廃業する人が多いのもまた事実です。
本記事では、なぜコンサル業は廃業しやすいのか、そしてそれでも“ITコンサル”という道に希望がある理由を、現実的な視点で解き明かしていきます。
コンサル業は廃業する人が多い?


なぜコンサル業は続かないと言われているのでしょうか?
そもそもコンサルティング業とは何か、そしてなぜ多くの人が開業し、なぜ失敗してしまうのかを整理してみましょう。
コンサルティング業とは
コンサルティング業とは、特定の分野における知識や経験を活かし、クライアント企業や個人の課題解決を支援する仕事です。
具体的には「経営の意思決定をサポートする」、「業務を効率化する提案を行う」、「ITシステムの導入を支援する」など、専門的な知見を用いて成果に貢献するのが主な役割です。
しかし、一口にコンサルと言ってもその種類は非常に多岐にわたります。
以下の表で、代表的なコンサル業の分類とそれぞれの支援内容をまとめてみました。
| コンサルの種類 | 主な対象領域 | 具体的な支援内容 |
|---|---|---|
| 経営コンサル | 経営戦略、人事、財務など | 経営改善、資金調達、組織改革 |
| ITコンサル | システム導入、DX、業務設計 | ITツールの導入支援、業務プロセスの可視化 |
| 人事コンサル | 採用、評価制度、研修など | 組織構築、評価制度設計、研修プログラム |
| マーケティングコンサル | 集客、ブランディング、販促 | 広告戦略、SNS運用、SEO対策 |
| 会計・税務コンサル | 財務、税務、資産管理 | 節税提案、財務アドバイス |
| M&Aコンサル | 企業買収・売却、事業承継 | 企業価値算定、交渉支援、手続き支援 |
このように、コンサルティング業は専門領域によって必要とされるスキルも異なり、多様化が進んでいます。
特に近年は、ITやマーケティングなどデジタル系コンサルのニーズが拡大しており、個人でも開業しやすい土壌が整いつつあります。
なぜコンサルティング業で開業するのか
コンサルティング業は、他の業種と比べて初期投資が少なく、個人でも始めやすいビジネスとして知られています。
オフィスや商品在庫が不要で、PCと知識さえあればサービス提供が可能なため、独立や副業の選択肢として注目されることが多いです。
以下のような動機や希望により、開業を目指す人が多くいます。
コンサル業の開業理由例
- 会社員時代に培った経験を活かしたい
- より自由な働き方をしたい
- 困っている企業や個人の役に立ちたい
- 専門知識に価値を感じてくれる顧客と直接つながりたい
- 自分の名前で仕事がしたい
実際にコンサルとして開業する人の多くは、企業で専門職やマネジメント経験を持つ中堅〜ベテラン層です。
経営企画、IT、営業、人事などの分野で豊富な実務経験を積んできた人が、自分のスキルを“個人の武器”として活かす場にコンサル業を選ぶことが多いのです。
また、近年はフリーランス向けのマッチングサービスやSNSを活用することで、営業力に自信がなくても案件を獲得しやすくなっているという背景も、独立への心理的ハードルを下げています。
しかし、開業当初は「自分の強みが市場にどう響くか」を見極める必要があり、過度な理想だけでスタートすると失敗しやすい一面もあります。
それでも、志を持って始める人が多いからこそ、コンサル業には“個の力”が色濃く反映されるのです。
失敗するコンサル業の特徴5選
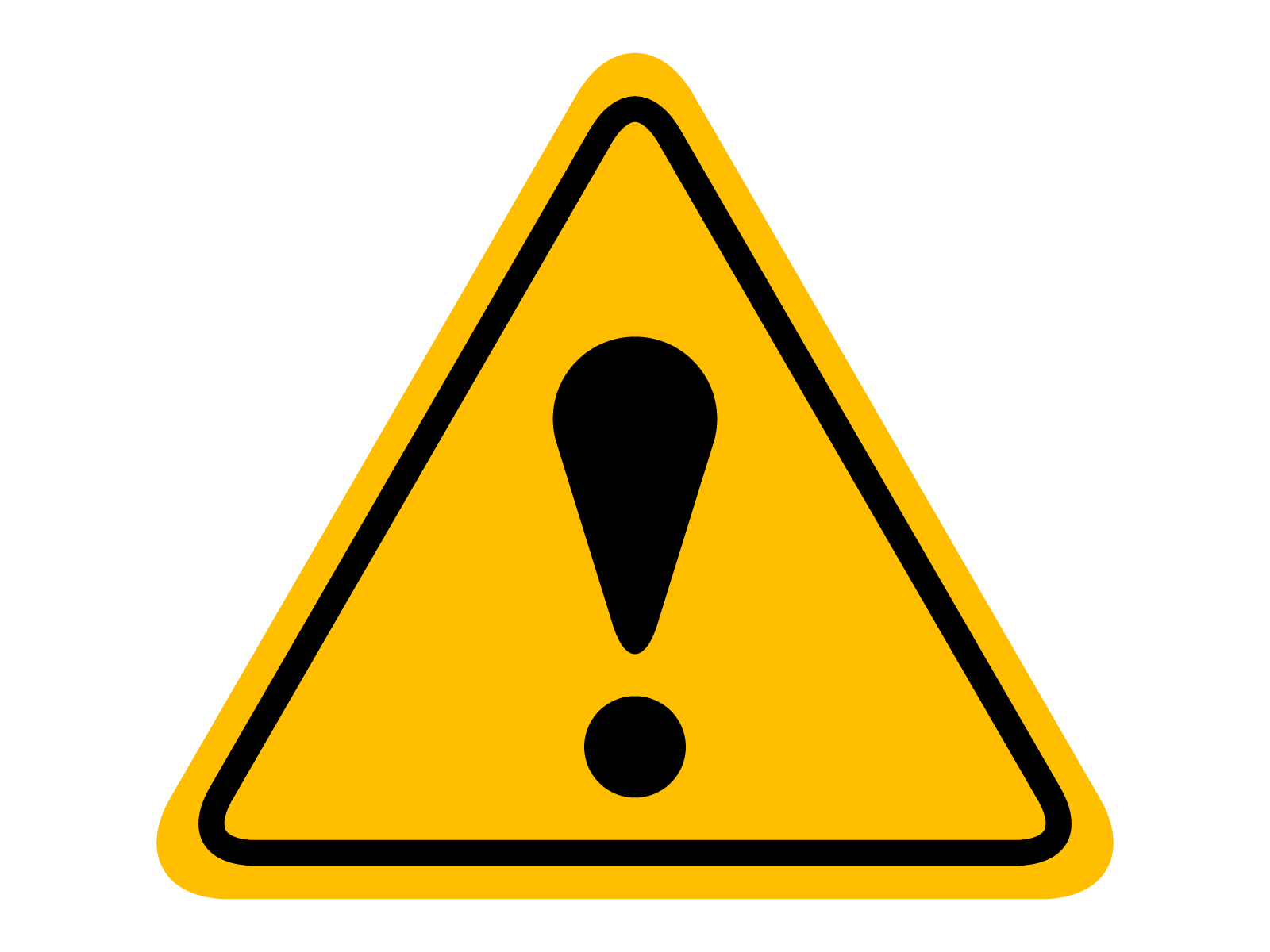
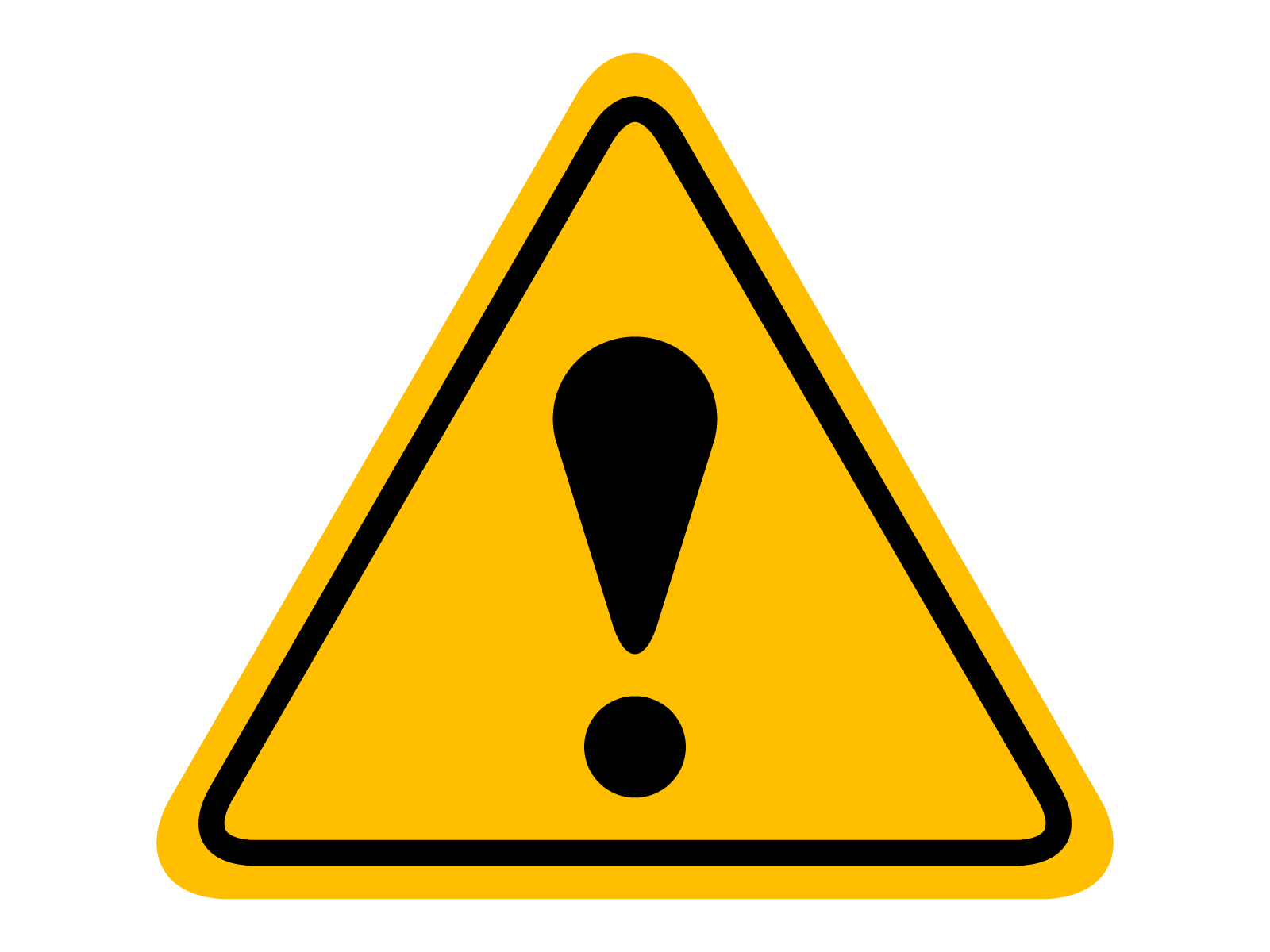
コンサルティング業で開業する人が多い一方で、廃業率が高いのもまた事実です。
その背景には「専門スキルはあるのに、事業として成り立たない」という“経営者としてのつまずき”が隠れています。以下に、特に多い失敗パターンを5つ挙げます。
失敗するコンサル業の特徴5選
- 自分の強みが曖昧なまま開業する
- 単価設計が甘く、安売りから抜け出せない
- 営業・集客の仕組みがない
- サービスの再現性が低い
- 時流に乗れず、情報発信が止まる
自分の強みが曖昧なまま開業する
「なんでも相談に乗れます」といったスタンスは、逆に誰にも刺さらず仕事に繋がりにくくなります。
自分の実績や支援分野を具体的に言語化できない人は、信頼を得るのに時間がかかりますので、“どんな仕事をしているのか”が誰が見てもわかるようにしておきましょう。
単価設計が甘く、安売りから抜け出せない
最初は実績作りと割り切っても、低単価を続けてしまうと収益が伸びない状態になってしまいます。
時間と労力ばかりを消耗して事業として継続できなくなってしまうため、単価を上げながら事業を進めていくイメージで、自分のスキルアップに常に挑みましょう。
営業・集客の仕組みがない
「紹介があれば」、「SNSで何とかなる」といった受け身の営業では、月ごとの売上が変動しやすく案件や売り上げが安定しません。
勝手に仕事が降ってくることはないので、地に足付けた活動を続けていくためにも営業力を付けたり、集客できるような仕組みを整える努力を怠らないようにしましょう。
サービスの再現性が低い
個別の対応力だけに依存すると、最初はよくても、事業が拡大してきたときに対応しきれなかったり、効率化できずに時間単価が低下します。
継続可能なサービス設計を組み立てられるように、改善改良を常に行っていくように心がけましょう。
時流に乗れず、情報発信が止まる
最新トレンドや業界変化を追えなくなると「頼れる専門家」としての価値が薄れる恐れがあります。
定期的なインプットと信頼構築のためのアウトプットを積み重ね、外部とのコミュニケーションを意識して取るようにしましょう。
※ このブログは創業22年のWeb企業「セルバ」が運営しています。
興味があれば[会社紹介はこちら]もご覧ください。
それでもITコンサルを目指すべき?


開業するからには、廃業のリスクが伴います。
年々コンサル業の廃業数が最多を更新し続けており、容易い道ではないことは容易に想像がつくと思います。
しかし、それでも「ITコンサルを目指したい」と考える人が後を絶たないのはなぜでしょうか?
ここではITコンサルという仕事の本質や、どんな人が向いているのか、開業後に気を付けるべきことを整理していきます。
ITコンサルとは
ITコンサルとは、IT技術を活用してクライアントの業務課題を解決する専門家のことです。
単にシステムやツールを提案するだけでなく「どんなITを、どの業務に、どう活用すべきか」という戦略立案から導入支援、運用定着までをサポートします。以下は主な業務領域の一例です。
ITコンサル業の業務領域▼
| 業務領域 | 主な内容 |
|---|---|
| DX推進 | 業務のデジタル化・クラウド移行の戦略立案 |
| IT導入支援 | ツールの選定・比較・導入プロジェクトの支援 |
| 業務改善 | ITを活用した業務プロセスの効率化提案 |
| システム選定・要件定義 | ベンダーとの橋渡しや仕様整理 |
| 情報セキュリティ支援 | セキュリティ対策や社内ルールの整備 |
必要とされるスキルは、ITに関する知識はもちろん、業務理解力・論理的思考力・課題発見力・コミュニケーション能力など、総合的なビジネススキルが求められます。
特に非IT系のクライアントと接する場面が多いため、専門用語をかみ砕いて伝える力や、現場視点での提案力が重要です。
ITコンサルは「技術の専門家」以上に、技術を“経営の言葉”に翻訳できる存在であることが求められます。
ITコンサルに向いている人の特徴5選


ITコンサルというと「高度なITスキルが必要」と思われがちですが、本当に求められるのは“人と課題に向き合う力”です。
むしろ、プログラミングや設計の専門家ではないからこそ、クライアントに寄り添えるポジションとして活躍できます。
以下のような性格的・仕事的な特徴を持つ人は、ITコンサルに向いている傾向があります。
ITコンサルに向いている人の特徴5選
- 相手の話をじっくり聞ける
- わからないことを素直に調べられる
- 抽象的な話をかみ砕いて整理するのが得意
- 過去のやり方に縛られず、柔軟に考えられる
- 相手の成功を“自分ごと”として考えられる
相手の話をじっくり聞ける
ITコンサルにおいて最も大切なのは、クライアントの話を丁寧に“聴く”姿勢です。
多くの経営者や現場担当者は、自分の課題をうまく言語化できていません。
表面的な言葉の裏にある「本当に困っていること」をくみ取るためには、相手の話を遮らず、共感しながら丁寧にヒアリングする力が求められます。
ただ質問を並べるのではなく、「なるほど、ではこういうことでお困りですか?」と咀嚼して返せる人は、相手からの信頼を得やすく、質の高い提案にもつなげることができます。
わからないことを素直に調べられる
ITの世界は変化が激しく、どんなベテランでも「知らないこと」に日々直面します。
そんなときに重要なのは知識の有無よりも、知らないことを放置せず自分から調べられる姿勢です。
特にITコンサルは、クライアントに対してベストな方法を説明する立場である以上、根拠のある知識に基づいた判断が求められます。そのためには、常に学び続けるスタンスが欠かせません。
「完璧じゃないから不安」ではなく、「学びながら進める自分を信じられるか」が大切なのです。
抽象的な話をかみ砕いて整理するのが得意
クライアントとの会話では「売上が下がっている」、「管理が煩雑」など抽象的な言葉が飛び交います。
ITコンサルはそれを業務フローや数値、システム要件に落とし込んでいく必要があります。
たとえば「請求業務が面倒」と言われたときに「どの作業が何分かかっていて、何が属人的か」まで分解し、具体的な改善ポイントに落とし込める人は強いでしょう。
論理的思考力というより、複雑なものを“わかりやすくする力”に長けている人が向いています。
過去のやり方に縛られず、柔軟に考えられる
システム導入や業務改善の現場では「ずっとこのやり方でやってきた」という固定観念とぶつかることがよくあります。そうしたときに「これが正しいです」と押し通すのではなく、「別のやり方もありますが、どちらが現場に合いますか?」と提案できる柔軟性が求められます。
特にITは正解が一つではない世界です。
自分の知識や経験をアップデートしながら、相手に合わせて選択肢を広げられる柔軟さが、信頼を生むコンサルの条件だと言えるでしょう。
相手の成功を“自分ごと”として考えられる
ITコンサルの本質は「助言すること」ではなく「相手が成果を出すまで伴走すること」です。
たとえばシステム導入後に運用が定着していなければ、機能的に成功していても意味がありません。
だからこそ、「提案したら終わり」ではなく「相手がちゃんと使えて成果につながっているか」を自分の責任として見届けようとする姿勢が重要です。
クライアントの課題を“他人事”にせず、自分ごとのように向き合える人は、長期的に信頼されるコンサルタントになれます。
逆に「自分の専門知識を披露したい」「指示される方が楽」と感じるタイプの人は、やや不向きと言えます。
ITコンサルに必要なのは、知識そのものよりも、対話・共感・論理性のバランスです。
開業後に気を付けるべきこと5選


ITコンサルとして開業するということは、単に「一人の専門家になる」ことではなく「経営者として自分自身を運営する」ことを意味します。
事業として継続していくためには、スキルや実務以上に、どんな意識で日々を積み重ねていくかが問われます。
以下に、コンサルタントとして開業した際に気を付けたい意識についてまとめておきます。
開業後に気を付けるべきこと5選
- 自分を“商品”として捉える視点を持つ
- 実力よりも“信頼”で選ばれるという現実を理解する
- 「選ばれる側」から「選ぶ側」への意識転換をする
- 決断をすべて一人で下すという現実を受け入れる
- “長く続けること”を目的にする
自分を“商品”として捉える視点を持つ
コンサルタントとして独立すると、多くの人がまずぶつかるのが「自分が何屋なのか伝わらない」という壁です。
実務経験やスキルは豊富でも、誰にどんな価値を提供できるのかを言語化できないと、選ばれることはありません。
名刺に肩書きを書いても、それだけでは仕事にはつながらないのです。
だからこそ、単なる“できること”の羅列ではなく、顧客が「この人なら解決してくれそう」と感じるような課題起点の提案力と自己定義力が求められます。
経営者としての最初の仕事は、自分という商品を明確にブランディングすることです。
実力よりも“信頼”で選ばれるという現実を理解する
どれだけITや業務改善の知識があっても、最終的に人が仕事を依頼するかどうかを決めるのは「この人に任せて大丈夫か」という信頼です。期待値を超える提案や実績も大切ですが、それ以上に重要なのは小さな約束を守る、丁寧に対応する、ミスがあったら真摯に謝るといった、地味な行動の積み重ねです。
特に独立後は、自分の振る舞いすべてがブランディングになります。
プロとしての実力を示す場面より、信頼を崩すリスクのある言動の方が多いことを意識しましょう。
信頼を積み上げることが、結果として選ばれる人になる最短ルートです。
「選ばれる側」から「選ぶ側」への意識転換をする
開業直後は、どんな仕事でもありがたく感じ、すべてを受けてしまいがちです。
しかし、単価が低すぎる案件や相性の悪い顧客に振り回されると、時間・気力・信用をすり減らすだけで終わってしまうことも。
経営者である以上、単なる「仕事をこなす人」ではなく、「誰とどんな価値を生み出すかを選ぶ人」という視点を持つ必要があります。
これは贅沢ではなく、事業として健全に続けるための戦略です。
自分の強みが最も発揮される領域に集中することで、単価も信頼も高まり、結果として無理のないビジネスの流れができていきます。
決断をすべて一人で下すという現実を受け入れる
独立すると、すべての判断を自分で下す必要があります。
案件の受注可否や価格設定、サービス内容の変更、トラブル対応などのあらゆる局面が存在します。
そんな中「最終的に責任を持つのは自分」だという現実に、想像以上にプレッシャーを感じる人は少なくありません。
相談できる上司も、守ってくれる組織もない中で、孤独をどう乗り越えるかは、開業における大きなテーマです。
自分の思考を整理する習慣を持ったり、定期的に話せる仲間やメンターをつくっておくなどして、孤独と向き合うための“覚悟と仕組み”の両方を備えられるようにしましょう。
“長く続けること”を目的にする
独立当初は売上ゼロの日が続いたり、SNSで他のフリーランスが華やかに見えて焦ったりすることもあるでしょう。
しかし、事業はマラソンのようなもので、一時的な成果ではなく「いかに信頼を積み上げながら続けられるか」が問われます。
売上やバズよりも、1人の顧客に丁寧に向き合い、その人に「またお願いしたい」と思ってもらえるかどうかが何よりも重要です。
派手な自己演出ではなく、地味な誠実さを積み重ねた人ほど、結果として長く信頼され、生き残っていきます。
目先の利益よりも「信頼資産の蓄積」という視点を持ちましょう。
まとめ
なぜコンサル業は廃業しやすいのか、そしてそれでも“ITコンサル”という道に希望がある理由について考察してきました。
コンサル業は、確かに厳しい世界です。
しかしその分、顧客に価値を届けられたときのやりがいは大きく、信頼が実績に変わる瞬間に大きな手応えを感じられる仕事でもあります。
もしあなたが「誰かの課題解決に力を尽くしたい」「自分の知識や経験を社会に活かしたい」と考えているなら、ITコンサルという道をキャリアの一つとして目指してみるのもいいのではないでしょうか。
セルバでは、ITコンサルに関する情報をYouTubeでも配信しています。興味のある方はぜひご覧ください!

