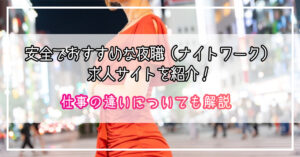スナック経営は厳しい?助成金は使える?統計や失敗例から学ぶ経営戦略
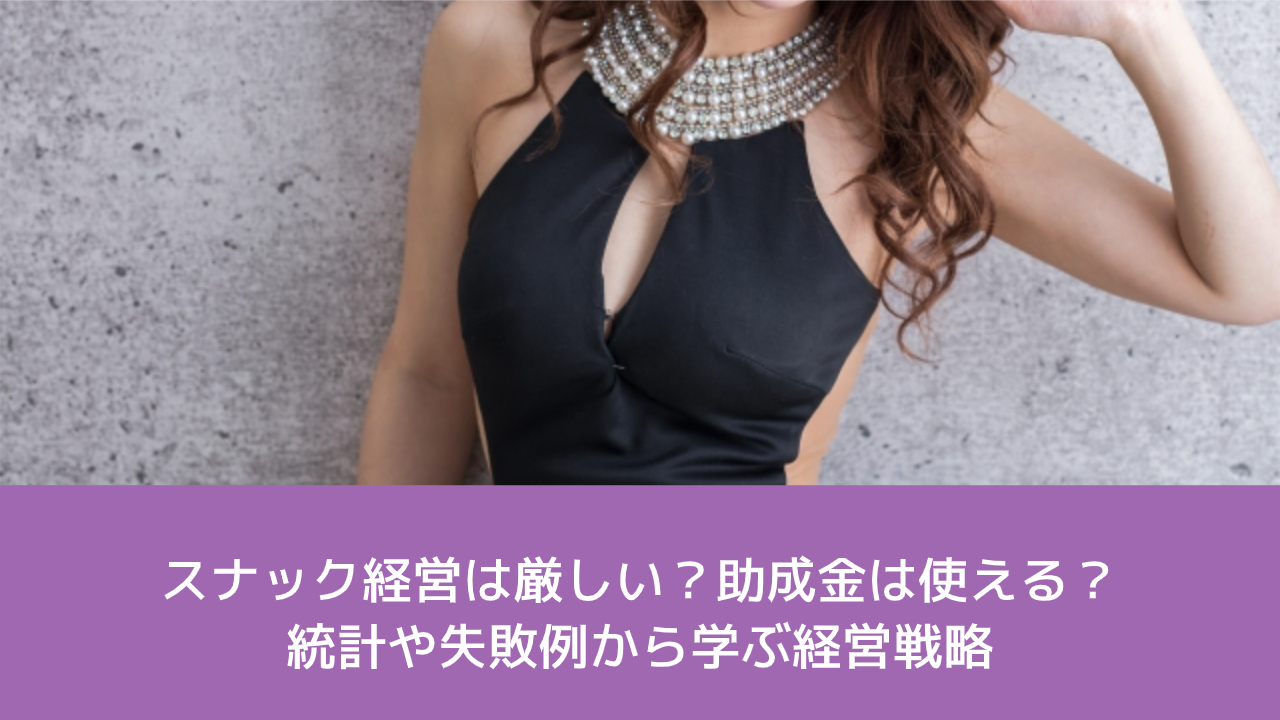
「自分のお店を持ちたい」という夢から、スナック開業を考える人は少なくありません。スナックで働いていた女性が独立するケースも多いです。
しかし現実には「スナック経営は厳しい」と言われ、廃業率も高い業態に数えられます。
なぜ多くのスナックが潰れてしまうのか。一方で、なぜ何十年も続くスナックが存在するのか。
本記事では、助成金や補助金の制度、失敗例や成功例を振り返り、「潰れないスナック経営」のヒントを探っていきます。
スナック経営が「厳しい」と言われる理由

スナックはキャバクラやガールズバーと比べ低コストで経営できるものの、維持するのは簡単ではありません。
スナック経営のデメリットとも言える「厳しい」と言われる理由を解説します。
売上は常連客に依存する
スナックは、キャバクラやガールズバーのように「新規客を大量に回転させる」ビジネスではなく、少人数の常連客に支えられる構造が特徴です。
そのため、特定の常連が転勤・引っ越し・健康上の理由などで来なくなると、売上が一気に下がります。
特に地方のスナックでは「数名の常連で成り立っている」といった極端なケースも珍しくありません。
裏を返せば、「人とのつながりが資産」なのですが、依存度が高すぎると経営リスクにも直結します。
飲食業界の廃業率が高い
飲食業界は全業種の中でも廃業率が高く、特に小規模店舗は経営が不安定になりやすいと言われています。
中小企業庁の調査によれば、飲食業の廃業率は全業種の中でトップの5.6%です。
帝国データバンクによると、2024年の飲食店倒産は894件に上り、前年から16%以上増加して過去最多となっています。
スナックは夜間営業が基本で、小規模店舗であることから、この倒産リスクの影響を強く受ける業態と言えます。
顧客の高齢化
スナックを利用する主な顧客は40代〜60代の中高年層です。
ところが、この世代がリタイアや健康問題で夜の街から足が遠のくと、売上は大きく落ち込みます。
若年層の飲酒離れや「スナック文化そのものに馴染みがない世代」の増加も加わり、新規顧客の獲得は簡単ではありません。
結果的に「顧客の高齢化」がそのまま売上の減少につながる構造が、経営を厳しくしています。
社会情勢の影響を受けやすい
スナックは夜間営業・接客業という性質から、社会的な変化の影響を強く受ける業態です。
例えばコロナ禍では、緊急事態宣言や時短要請によって営業停止に追い込まれ、多くのスナックが廃業しました。
補助金が出ても十分ではなく、「数十年続いた老舗が閉店する」という事態も各地で起きました。
景気後退や物価高騰の影響も受けやすく、酒類の仕入れや光熱費の高騰は直ちに経営を圧迫します。
社会情勢に左右される脆弱さが、スナック経営を難しくしているのです。
スナックの開業・経営に助成金・補助金は使える?

資金面での苦労を減らすために、国や自治体の助成金・補助金制度を活用することは重要ですが、実はスナックの開業や経営でも活用することができます。
代表的なのが「小規模事業者持続化補助金」で、販路開拓や業務効率化のために50万~250万円が支給されます(補助率2/3~3/4)。
スナックの開業や経営に必要な、内装費や広告宣伝費に充てることができます。
東京都では、創業から5年未満の事業者に100万~300万円を支給する「創業助成金」が存在し、地方でも同様の制度を設ける自治体があります。
POSレジや予約システム導入に使える「IT導入補助金」もあります。
補助額は5万〜3,000万円、補助率最大4/5と幅広く(IT導入補助金公式)、デジタル化による効率化を進める際に大きな助けとなります。
セルバでは90%を超える採択率の助成金・補助金申請サポートのサービスを行っています。
興味がある方はお気軽にお問い合わせください。
スナック経営に潜むトラブルと失敗事例

スナックは人間関係が狭く濃い傾向にあります。
そのぶん経営では、人間関係や金銭管理など、小さなトラブルが命取りになることがあります。
出資者とママの関係が悪化
スナックの開業では、資金を出す人(出資者)と実際に店を切り盛りするママが別の場合も少なくありません。
最初は「一緒に盛り上げよう」と意気投合していても、売上が思ったように伸びなかったり、経費の使い方で意見が食い違ったりすると、関係が悪化することがあります。
出資者から「もっと利益を出してほしい」とプレッシャーがかかり、ママが「お客様との関係を大事にしたい」と衝突するという構図は珍しくありません。
実際に大阪・心斎橋の事例では、出資者とママの関係がこじれて開店から数カ月で閉店に追い込まれたケースが報告されています。
ところが中には、新規開業から間もなく閉店をむかえる、という方もいらっしゃいました。
引用元:ミナミ心斎橋エリアでの「新規スナック開業時の失敗2つの事例」
(中略)
お店の運営について意見が分かれ、出資者と店長さんの仲が段々と悪くなり、ついにはお店を開けられなくなり、閉店⇒物件解約といった事例がありました。
経営に携わる人同士の信頼関係を維持することは、数字以上に重要な条件です。
ツケ払い・未収金の問題
昔ながらのスナックには「ツケで飲む」という文化が残っていることがあります。
常連客との信頼で成り立つ部分であり、未払いが続くと当然経営を圧迫します。
小規模なスナックでは、数十万円の未収でも致命傷になりかねません。
実際に「未収金が100万円を超えて資金ショートし、廃業に追い込まれた」という事例もあります。
現代ではキャッシュレス決済や前払い制を導入する店舗も増えており、こうしたリスクを減らす努力が必要です。
「お客様との信頼関係」を理由にルーズな管理を許すのは、結果的にその関係すら壊しかねないのです。
スタッフの突然の退職・人手不足
ママ一人で回しているお店もありますが、多くのスナックは女性スタッフに支えられています。
しかし、夜の仕事は不規則な生活や人間関係のストレスから離職率が高く、急な退職に直面することも少なくありません。特に地方では代わりをすぐに見つけられず、人手不足で店が回らなくなることもあります。
大阪・心斎橋の事例でも、スタッフが急に辞めてしまい営業継続が困難になったケースが紹介されています。
「オープン直前に店長予定者が辞めた」という話も意外とよく耳にします。
当然、店長予定者がいなくなればお店も開けられないので、やむなく閉店⇒物件解約となってしまいます。
引用元:ミナミ心斎橋エリアでの「新規スナック開業時の失敗2つの事例」
人材を採用するだけでなく「定着させる」工夫として、労働環境の改善や人間関係づくりが、スナック経営の持続には欠かせません。
風営法違反による営業停止
スナックは風営法の規制対象であり、営業時間・接待行為・照明などに細かいルールがあります。
たとえば、接待飲食等営業の許可がないのに女性スタッフがお客様の隣について会話を続けたり、深夜2時以降も営業を続けたりすれば、行政処分や営業停止のリスクがあります。
摘発されれば営業停止に追い込まれ、信用は失墜し、事実上の廃業にも直結します。
悪気があって故意に違反したわけではなく、法律の理解不足や「うちは大丈夫だろう」という見通しの甘さから違反してしまうケースがほとんどですが、安定して営業を続けるためには、法令遵守の姿勢を徹底することが最も重要だと言えるでしょう。
スナックが潰れない理由

スナック経営が厳しいと言われる一方で、一見あまり流行っているように見えなくても、潰れず何十年も続いているスナックもあります。
そういったお店には、共通する理由があります。
お客様への感謝を大切にしている
長く続くスナックのママやスタッフに共通するのは、常に「お客様への感謝」を忘れない姿勢です。
お礼の言葉や細やかな気配りはもちろん、誕生日や記念日を覚えてちょっとしたプレゼントを渡すなど、日常的に「ありがとう」を伝える工夫をしています。
長く人の上に立つ社長さんは腰が低くて、敵を作らない人が多いと思います。そして「ありがとう」とか「ごめんなさい」とか、そういう言葉がサラッと言える人が経営する会社は長く続いている印象を受けますね。
そういう人は、周りが助けてあげたくなるからではないでしょうか。そもそも、仕事は一人じゃできませんよね。自分が困ったときに手を差し伸べてくれる人がいるとか、困っている人に手を差し伸べることができるとかって、ビジネスをする上で非常に重要なことだと思うんです。
それと、そういう言葉が言える人って、基本的に笑顔が多いんですよ。そうすると、自然と周囲に人が寄ってくるんです。どんな会社でも仕事でも、人に愛されないと続かないじゃないですか。
引用元:〜40年続く老舗スナックのママに聞いてみた〜フリーランス・経営者が成功するための秘訣は?
こうした心のやり取りが信頼を育み、「この店だから通いたい」という気持ちを生み出しているのです。
経営の数字以上に、人との絆はスナック経営の基盤になっています。
コストを下げても顧客満足度が下がらない仕組みができている
スナックは決して高級店ではなく、むしろ「手頃な価格で長く通える」ことが魅力です。
長寿店は、原価率の高い高級酒に頼らず、ボトルキープや飲み放題セットなどで工夫して、コストを抑えながらも顧客が満足できるスタイルを確立しています。
ママやスタッフとの会話やお店の雰囲気といった「人の価値」が提供の中心になるため、金銭的な負担が少なくても満足度が高いのです。コストと満足度のバランスを保てる仕組みが、経営を支えています。
リラックスできる「サードプレイス」になっている
仕事でも家庭でもない「第三の居場所(サードプレイス)」として機能していることも、潰れないスナックの特徴です。
気軽に立ち寄って愚痴をこぼしたり、孤独を癒したりできる場所になることで、長年の支持につながります。
肩肘張らずに過ごせる雰囲気を作るために、「ただ話を聞く」ことに徹するママやスタッフも珍しくありません。
安心して本音を出せる空間であることが、最大の強みになっています。
常連と新規顧客のバランス
長寿スナックは常連を大切にしつつも、新規顧客を受け入れる柔軟さも持っています。
常連だけの閉じた空間になると新しいお客様が入りにくく、徐々に衰退してしまいます。
そこで、イベントや紹介制を取り入れて新しい人が入りやすい雰囲気を作ったり、SNSでの発信で若い世代を呼び込んだりしています。
結果として「顔なじみの安心感」と「新しい出会いの楽しさ」が共存し、店が活気を失わずに続いていくのです。
時代に合わせた柔軟な変化
老舗であっても、長く続くスナックは「昔ながら」だけに固執しません。
キャッシュレス決済の導入や、SNSによる集客、店内のレイアウト変更など、時代に合わせた小さな変化を取り入れています。
大きく方向転換をするのではなく、あくまで自分たちの持ち味を残しつつ、必要な部分をアップデートする姿勢が強みです。
変わらない安心感と、新しさのバランスを取り続けることが、長寿スナックの共通点となっています。
地方でのスナック経営

地方でのスナック経営は人口減少で人材獲得や集客に不利な一方、競合が少なく、地域の「社交場」としての役割を果たすことで息の長い経営が可能です。
葬儀後の会食や町内会の集まりなどに利用され、安定した売上を維持している例もあります。
地域の資源と飲食店を結びつける「ガストロノミーツーリズム」という観光庁の取り組みもあります。
潰れないスナックの共通点を踏襲しつつ、地元の酒や食材を取り入れることで、地域にも貢献し長く支持されるお店になる可能性があります。
Webでできるスナックの集客方法

スナックの集客はチラシや看板など、今でもオフラインがメインではありますが、今やスナック経営にもデジタル集客は欠かせません。
夜職ポータルサイト
スナック経営において新規顧客の集客力が最も高いのは、夜職向けのポータルサイトです。
キャバクラ・ガールズバーしか掲載できないイメージがあるかもしれませんが、スナックも掲載できるところが多いです。
地域や料金体系で検索するユーザーが多く利用しており、特に40〜60代の男性客はSNSで飲み屋を探すよりも、こうしたポータルで「安心して入れる店」を比較する傾向があります。
料金システムや営業時間を明示することで安心感を与えられるのも大きなメリットです。
スナックは“隠れ家的”な魅力を持ちつつも、初めての人が「ここなら安心」と思える入り口を作ることが重要であり、ポータル掲載は即効性のある集客施策だと言えます。
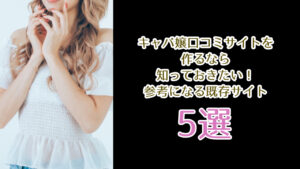
LINE公式アカウント
リピーターを確保するために欠かせないのがLINE公式アカウントです。
友だち追加をしてくれた顧客に対して、イベント情報やキャンペーン、誕生日のお祝いメッセージなどを直接届けることができます。
例えば「次回ボトル1本サービス」といった特典をつけて来店を促すほか、常連が来なくなるリスクを減らせるのが強みです。
SNSのように不特定多数に拡散するのではなく、“常連顧客と1対1でつながる仕組み”として活用するイメージです。
40〜60代の男性でもLINEは日常的に使っているため、スナックとの相性は非常に良いといえます。
Instagram / Facebook
複数のSNSがある中で、スナックの集客におすすめなのはInstagramとFacebookです。
Instagramは女性スタッフの獲得や女性客を取り込みたいときの訴求に効果的で、店内やカラオケイベントの写真を投稿することで「行ってみたい」と思わせるきっかけを作れます。
Facebookは40〜60代の利用者が多く、地域コミュニティやグループ機能を活用して地元住民にリーチしやすいのが利点です。
スナックの集客は口コミが基本ですが、インスタで「雰囲気の発信」、Facebookで「地域とのつながり」を強めることで、常連層に加えて新しい客層を呼び込む可能性が広がります。
まとめ
スナック経営は、統計や事例が示す通り厳しいと言っても過言ではない業態です。
廃業率は高めで、資金繰りや人間関係の失敗で短期間に閉店に追い込まれるケースも少なくありません。
しかし、助成金や補助金を賢く活用し、無理のない規模で常連客や地域コミュニティとのつながりを築けば、長く愛される店に育てることも可能です。
スナックは単なる飲食店ではなく、地域の社交場であり、人と人が支え合う文化が息づく場所です。
リスクを理解し、工夫を重ねることで、「厳しい」と言われる業界の中でも持続可能な道を歩むことができます。
セルバでは夜職関係のポータルサイトの制作実績や、求職者の集客実績があります。
スナック、キャバクラ、ガールズバーの集客や人材確保にお困りの方は、お気軽にご相談ください。