ROM専はうざい?賢い?企業目線で存在意義について考える

「ROM専」は、発言せず閲覧のみを行うユーザーを指す言葉です。
近年、ネット上では「うざい」「いらない」といった否定的な評価も見られますが、果たして彼らは本当に価値のない存在なのでしょうか。
本記事では、ROM専に関する検索動向や世間の見方をもとに、その存在意義を企業視点で考察します。
ネットに潜む“見るだけ勢”の実態

「ROM専」とは「Read Only Member」の略。要するに、見るだけで発言しないユーザーのことです。
SNSでも掲示板でもYouTubeでも、誰かがコメントを投稿すれば、それを黙って見ている人が必ずいます。
投稿しないからと言って、無関心というわけではありません。
むしろ、情報をじっくり観察して、流れを理解して、空気を読む。そのスタンスから、「ROM専=賢い」という評価もチラホラ見かけます。
とはいえネットの空気は一枚岩ではありません。
「rom専 うざい」「rom専 いらない」「rom専 死語」……など、なかなかキツめのワードも見受けられます。
一体なぜ、ROM専はここまで物議を醸す存在となっているのでしょうか?
「ROM専 うざい」は月間590件検索されている
まずはデータを見てみましょう。「ROM専」に関するキーワードが、月間でどのくらい検索されているかをご紹介します。
- ROM専:2,900件
- ROM専 うざい:590件
- ROM専 今の言い方:210件
- ROM専 死語:210件
- ROM専 マナー:170件
- ROM専 賢い:140件
- vtuber ROM専 いらない:110件
どうやら、ROM専は「うざい」と感じられたり、「マナー違反」と見なされたりすることもあるようです。
逆に「賢い」と褒められることもあり、意見はかなり分かれている模様。
まるで人類全員が“野次馬”か“審判”かで争っているようなこの状況。
企業ブログ的には、「なぜここまで意見が分かれるのか?」を掘り下げてみる価値がありそうです。
ROM専マナー論争 |「黙って見る」は失礼なのか?
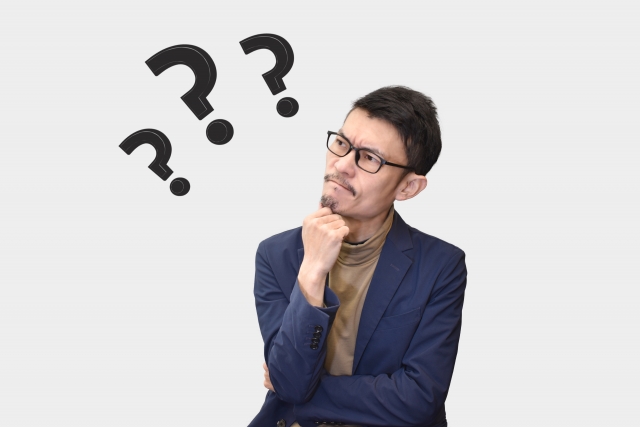
SNS上で度々見かけるのが

いいねもRTもせずに見るだけって失礼じゃない?
という意見。
Vtuber界隈などでは、「ROM専はいらない」と断言するような空気感も一部に見られます。
その背景には、「コンテンツを無料で楽しむなら、せめて反応ぐらいはしてよ」という心理があります。
つまり、「受け取るなら返礼を」という“ネット上の互助精神”が、ROM専を非難する根拠になっているのです。
とはいえ、それって本当に正義でしょうか。
コンテンツを無料で公開しているのは、コンテンツ制作側にもメリットがあるからです。
無料で公開したくないのであれば、課金しないと閲覧できないエリアでのみ公開すればいい話なのです。
「静かにしてるだけなのに責められる」というのは謎ですよね。
ROM専こそ賢い?
一方で、「ROM専はむしろ賢い」という見方もあります。
- 余計なことを言わない
- 炎上に巻き込まれない
- コミュニティの空気を乱さない
- 常に状況を観察し、学びに徹する
こうして見ると、確かに賢者っぽいですよね。
コメント欄で火花を散らすタイプより、ずっと落ち着いていて思慮深い印象すらあります。
ネットにおいて“声の大きい人”が必ずしも“影響力のある人”とは限りません。
むしろ、静かに見ている大多数のROM専が、コンテンツの寿命を支えているケースが多いのです。
企業にとってROM専は「見えない顧客」そのもの


マーケティングの世界には「99:1の法則」があります。
これは、コミュニティの中で積極的に投稿・反応するのは全体の1%、残りの99%は見るだけという理論です。
つまり、ネット上の「ROM専」は決して無関心なわけではなく、しっかり見ているが発言はしない“見えないファン”なのです。
- PV(ページビュー)を稼いでくれる人
- 離脱せず、最後まで記事や動画を読んでくれる人
- サイレントに商品を購入する人
コメントが無いからといって「反応が悪い」と判断するのは早計です。
これは、一部の声の大きいユーザーの声ばかり気にするのも良くないという話でもあります。
大多数のROM専ユーザーは問題なくコンテンツを楽しんでいるのに、一部の声の大きいユーザーの声を反映して、本来変えなくても良かった部分を変えてしまわないように注意すべきと考えます。
※ このブログは創業22年のWeb企業「セルバ」が運営しています。
興味があれば[会社紹介はこちら]もご覧ください。
Vtuber界隈の一部ではなぜ「いらない」扱いされるのか


注目すべき検索キーワードの一つが「vtuber rom専 いらない」(月間平均検索ボリューム110件)。
Vtuber文化は「推し活」によって支えられている世界です。
ファンがコメントをし、スパチャを投げ、SNSで拡散してくれることで、コンテンツが成長します。
そのため、「ROM専=何も貢献しない人」という見方をされがちです。
でもここで、“貢献の定義”を見直してみませんか?
- 再生数に貢献している
- 報告しないけどグッズは買っている
- ファンであることを公言しないけどチャンネル登録やSNSのフォローはしてくれる
こういった“静かなファン”も立派なサポーターです。
むしろ、過激に盛り上がるファンダムより、長期的に安定して応援してくれるROM専の方が、企業にとってはありがたい存在であることも少なくありません。
ROM専は死語なのか?


「rom専 死語」というキーワードも、月間検索ボリュームは210件と、少なくはありません。
確かに、最近では「ROM専」という言葉自体をあまり聞かなくなりました。
むしろ進化している
SNS世代にとっては、「見る専」や「リスナー」という表現の方が主流かもしれません。
でも、それは言葉が進化しただけで、存在そのものが消えたわけではないのです。
- Slackやchatworkを確認はしているものの、発言もリアクションもしない社員
- YouTubeで毎日見てるのに、いいねもコメントもしない視聴者
- クレームもお礼も言わないが、週に数回飲食に来てくれる顧客
彼らは“現代型ROM専”と言えます。3つ目に至っては遥か昔から存在します。
形を変えながら、今もどこかで、確実に「見て」います。
死語ではなく、呼び方が変わっただけと言えます。
社内にもいる!ROM専社員あるある


企業の中にも所謂ROM専はいます。
SlackやChatworkを見ているのに、発言もリアクションもゼロという方、見覚えありませんか?
- ミーティングではずっとミュート、でも内容は全部聞いている
- 社内イベントには参加しないけど、写真はしっかり見ている
- 社報やプロダクト資料を全部チェックしてるけど、感想は言わない
- 社内の空気を読んでいるが、何も言わない
こういう人たち、意外と頼れる存在だったりしますよね?
もちろん状況によっては、「気づいているなら早めに指摘してほしかった」「見ているなら何かしら報告くらいはしてくれないと困る」ということもあると思いますが、彼らを「参加する気がない」と判断するのは早いです。
ROM専を切り捨てるのは早い!企業が見落としがちな“声なき声”
ネットでも社内でも、つい目立つ人や声の大きな人に目が行きがちです。
しかし、「何も言わない人=何も思っていない人」ではありません。
むしろROM専のような“観察者”たちは、場の空気や変化に敏感で、感情や考えを内に秘めていることが多いです。
彼らの存在を認識し、意思を尊重することが、真に成熟したコミュニケーション設計につながるのです。
企業として大事なのは「見えないけど確実に存在する人たち」をどう扱うか
- コンテンツを見てるけど反応しない人
- サービスには満足しているけど声を上げない人
- 改善点に気づいてるけどあえて言わない人
こういったROM専的存在こそ、丁寧に向き合う価値があります。
フィードバックが無いからといって、「反応が悪い」と即断しない姿勢が、これからの企業には必要不可欠です。
- 無理に発言を求めず、「問題なければリアクションのみで大丈夫です」と一言添える
- フィードバックは「忖度なしで教えてください」と伝えて匿名フォームで受け付ける
- 「いつも見てくださってありがとうございます」とたまには感謝を伝える
ROM専は“静かなるインフラ”である
多くのサービスやコミュニティにおいて、大多数のユーザーはROM専です。ただ「何もしない人」ではなく、「場の根っこを支えている人」と言えます。
- コンテンツの再生数を支える
- 炎上を起こさずに健全な空気を保ってくれる
- 声を出さなくても、情報を受け取り、広めてくれる
目立たず、冷静にネットを見つめている彼らは、もしかするとインターネット社会における“静かなるインフラ”なのかもしれません。
インターネットの変遷には、まだまだ語りきれない話がたくさんあります。
気になる方は、ほかのコラムも読んでみてください。


