mixiは本当に終了したのか?かつての栄光と現在を徹底解説
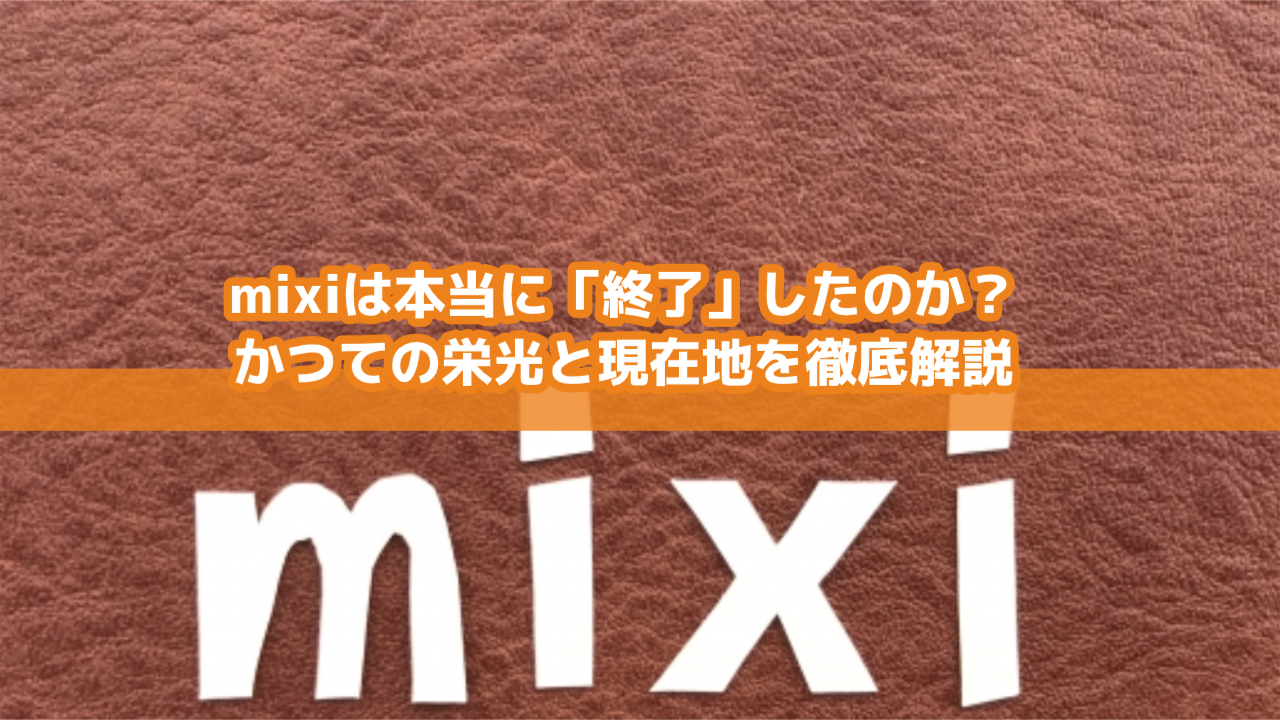
2004年に誕生したSNS「mixi(ミクシィ)」。
「足あと」や「コミュニティ」など独自の文化を生み出し、2000年代半ばには国内SNSの代名詞として社会現象を巻き起こしました。
しかし近年、検索エンジンには「mixi 終了のお知らせ」「ミクシィ 終了 なぜ」といったサジェストが並び、「まだやってる人はいるの?」「mixiはどこへ行った?」と疑問を持つ方も多いことがわかります。
今回は、mixiの誕生から黄金期、事件や転機、衰退の背景、そして現在の姿までを網羅的に整理します。
mixi誕生と急成長の軌跡

2000年代半ば、日本のインターネット文化は大きな転換期を迎えていました。
掲示板の2ちゃんねるや個人ブログが主流だった時代に、「友人とオンラインでつながり、日常を共有する」という新しい体験を提示したのがmixiです。
2004年の誕生からわずか数年で会員数は急増し、テレビや雑誌でも特集が組まれるなど、社会現象級のムーブメントとなりました。
今でこそFacebookやTwitterに慣れ親しんだ私たちですが、当時の日本人にとってmixiは、初めて「SNS」という言葉を実感させる存在だったのです。
日本初の本格的SNS
2004年2月、株式会社イー・マーキュリー(後のミクシィ社)が「mixi」を開始。
当時は招待制で、限られたユーザーが安心して使えるクローズドなSNSとして人気を博しました。
- 足あと機能:自分のページを誰が見に来たかが分かる仕組み
- コミュニティ機能:趣味や属性ごとに交流できる場を提供
- 日記・コメント文化:現在のタイムライン投稿の原型ともいえる形式
黄金期:2008年前後
- 会員数は2008年時点で1,500万人を突破
- 日本のSNS市場シェアは70%以上を占有
- 芸能人や企業アカウントも続々参入
この時期、mixiは「実名のFacebook」「匿名掲示板の2ちゃんねる」と並ぶ第三の居場所として、国内ネット文化の中心を担っていました。
mixiを揺るがした事件と課題

栄光のピークを迎えたmixiでしたが、その後の歩みは決して順風満帆ではありませんでした。
利用者数が拡大するにつれ、機能変更によるユーザー離れや、不正利用・トラブルによるブランド毀損が相次ぎ、サービスの基盤を揺るがす出来事が立て続けに発生します。
中でも「足あと機能廃止」をめぐる混乱や、出会い目的の利用拡大は、ユーザーの信頼を失わせる決定的な要因となりました。
mixiの衰退を加速させた主要な事件と課題を振り返ります。
CSRF(クロスサイトリクエストフォージェリ)脆弱性問題(2005年頃)
mixi上で悪意あるリンクをクリックするだけで、ユーザーの日記に「ぼくはまちちゃん!」という投稿が勝手に書き込まれるという現象が多発しました。
これはサイト側のセキュリティ上の不備(CSRF脆弱性)によるもので、一時的ながら不安定なユーザー体験を招きました。
出典:ITmedia
薬物密売トラブル(2007年6月)
SNS内のコミュニティを通じて、向精神薬「リタリン」が不正に売買された事件が発生しました。
熊本県警が捜査に乗り出し、不正アクセス禁止法・薬事法・麻薬取締法違反などで容疑者が逮捕されています。
SNS上での違法薬物取引は、mixiの管理体制が問われる社会的事件でした。
出典:J-CAST ニュース
足あと機能廃止(2011年6月)
長年mixiの象徴的機能だった「足あと」機能が2011年6月に廃止され、「先週の訪問者」としてまとめて表示される形式に変更されたことは、大きな波紋を呼びました。
ユーザーからは

誰が自分のページを見たのかがわからなくなった!
と強い反発もありました。
出典:ITmedia
※ このブログは創業22年のWeb企業「セルバ」が運営しています。
興味があれば[会社紹介はこちら]もご覧ください。
mixi終了の誤解と真実


インターネット上ではしばしば「mixiはもう終わった」「サービス終了した」という声を目にします。
検索候補に「mixi 終了のお知らせ」などが並ぶこともあり、多くの人が「mixiはすでに存在しない」と思っていますが、結論から言うとこれは誤解です。
サービスは終了していない
多くの人が「mixiは終了した」と思っていますが、現在もサービスは継続中です。
公式サイトからログイン可能で、アプリも存在します。
ただし、全盛期からは大きく姿を変え、機能縮小や利用者数の減少が進んでいるため、「終了したかのように見える」状況になっているのです。
2025年現在の会員数は公表されていませんが、一部調査では数百万人規模で細々と稼働しているとされています。
「終了のお知らせ」とは何か?
「mixi 終了のお知らせ」というサジェストが出てくる理由は、mixi自体がの終了したということではなく
- コミュニティ機能の一部停止
- 足あと機能終了
- ゲーム機能終了
など、機能縮小に関する告知が原因だと思われます。
まだmixiをやっている人はいるのか?





mixiって、もう誰も使ってないんじゃないの?
そんな声を耳にすることは少なくありません。
確かにSNSの主役の座をTwitter、Instagramに譲って久しいですが、だからといってmixiが完全に忘れ去られたわけではありません。今もログインを続けるユーザー層が存在し、独自の目的で活用されているのです。
どのような人々が現在もmixiを利用しているのか、その実態に迫ってみましょう。
実際の利用者層
「mixi まだやってる人」というキーワードが示すように、今も一定数のユーザーは存在します。
- 2000年代からの古参ユーザー
- コミュニティをアーカイブ的に利用する人
- 出会い目的で使う層
特に「出会い系」の温床になっている現状は、かつての健全イメージから大きく変化しています。
利用者アンケートでみる現在のmixi
2022年にmixi公式が実施したアンケート調査(回答数2,256件)によると
- 毎日利用する人は約7割
- 利用目的は「近況報告」「同じ趣味の人を探す」「雑談」が上位
- 満足している人(非常に満足+満足)は46.1%
一般的な認知度は低下していても、既存ユーザーには継続利用されているプラットフォームであることが分かります。
mixiと「出会い」文化
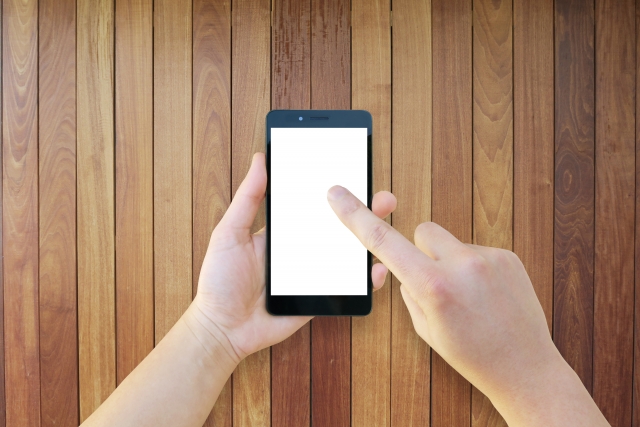
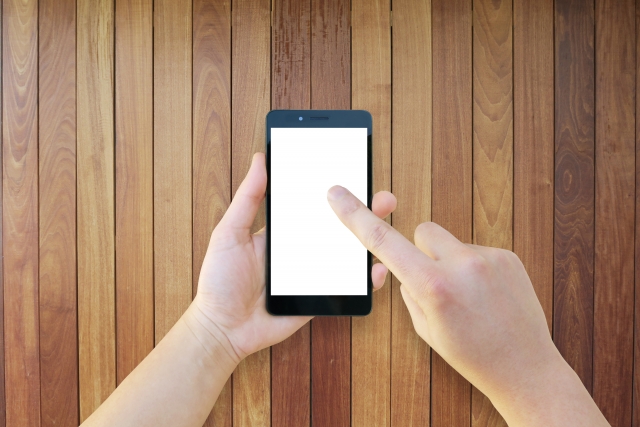
SNSの利用目的は本来「友人や知人とのつながりを深めること」にありました。
しかし、mixiの成長とともにユーザー層が広がり、やがて一部では「新しい人との出会い」を主目的とする使い方が顕著になっていきます。
匿名性が高く、共通の趣味や関心事でつながれるmixiは、従来の出会い系サイトよりも敷居が低く、自然に関係を築ける場として注目を集めました。
結果として「mixi=出会える場所」というイメージが形成され、サービス全体の評価やブランドにも大きな影響を及ぼすことになったのです。
出会い目的化した背景
mixiは当初、友人や知人同士の交流を深めるためのSNSとしてスタートしました。
しかし次第に「知らない人と出会う」目的で利用するユーザーも目立つようになっていきます。
その理由のひとつが匿名性の強さでした。
Facebookのような実名制SNSとは異なり、mixiではニックネームやハンドルネームでの利用が主流。これによりユーザーは素性を明かさずに交流でき、心理的なハードルが低くなっていたのです。
また、当時のmixiには数え切れないほどの「趣味コミュニティ」が存在しました。
音楽、映画、ゲーム、恋愛相談、アルバイトなど多種多様なテーマで人々が集まり、掲示板形式で会話を楽しめました。
その延長線上で、気の合う相手とオフラインで会う流れが自然に生まれ、やがて「mixi=出会える場所」というイメージが広まったのです。
社会的議論
2007年には、mixi内の一部コミュニティが実際に「出会い系サイト的」に使われ、未成年ユーザーや業者によるトラブルが問題視されました。
特に薬物売買や援助交際などの事例が報道され、運営側の管理体制に厳しい目が向けられたのです。
こうした事件は「ミクシィ事件」として世間に知られるきっかけとなり、SNSが抱えるリスクを可視化する出来事でした。
運営側の対応とその限界
ミクシィ社も事態を重く見て、2009年以降は「出会い系的コミュニティ」を一斉削除するなど健全化を進めました。
利用規約の強化や通報機能の整備も行い、未成年を守る施策も導入しました。
しかし、ユーザーの意識までは完全にコントロールできず、「裏コミュニティ」や「サークル外の個人的やり取り」での出会い目的で利用するユーザーは残り続けました。
現在のmixiにおける出会い
2020年代のmixiはかつてほどの影響力は持ちませんが、検索をかければ「出会い」を目的に使っているユーザーは依然として存在します。
他のSNSに比べて「人の目に触れにくいクローズド感」が残っているため、一定の層には根強く支持されているのです。
もっとも、現代ではTinderやPairsといったマッチングアプリが主流となっているので、mixiでの出会い利用は限られた小規模な動きに縮小しています。
ミクシィ社の事業転換と現在


SNSとして一世を風靡したmixiでしたが、利用者数の減少は止まらず、サービス単体での成長は頭打ちになっていきました。
そのなかで運営元である株式会社ミクシィ(現MIXI)は、早い段階から「SNS企業から総合エンタメ企業へ」と戦略を切り替えていきます。
特に2013年にリリースしたスマホゲーム『モンスターストライク』の大ヒットは、同社の事業構造を劇的に変化させ、SNS事業が主役から脇役へと移行する大きな転換点となりました。
ミクシィ社がどのようにして新たな収益モデルを築き、現在どの位置に立っているのかを整理していきます。
株式会社ミクシィ(現MIXI社)の戦略
- 2013年:スマホゲーム「モンスターストライク」が大ヒット
- 2015年以降:SNS事業からエンタメ・スポーツ事業へシフト
- 2021年:社名を「MIXI株式会社」に変更
いまや「ミクシィ=SNS」ではなく、「MIXI=モンストの会社」という認識が一般的です。
年表でたどるmixiの歴史
| 年月 | 出来事 |
| 2004年3月 | 「mixi」正式オープン。招待制で開始。 |
| 2007年2月 | 会員数1,000万人突破。 |
| 2008年11月 | 招待制を廃止、登録制へ移行。年齢制限を15歳以上に緩和。 |
| 2010年 | 完全登録制へ移行。 |
| 2011年6月 | 「足あと」を「先週の訪問者」へ変更し大きな議論に。 |
| 2013年10月 | 「モンスターストライク」提供開始。 |
| 2017年1月 | モンスト利用者数4,000万人。ミクシィの収益構造が完全にゲーム依存に。 |
| 2024年12月 | 新SNS「mixi2」をリリース。従来mixiとは互換なし。 |
mixi2の登場
2024年12月、MIXI社は完全招待制のSNS「mixi2」をリリースしました。
「今を共有でき、すぐ集える」をコンセプトに、従来のmixiとは別サービスとして運営されています。
アルゴリズムよりも人間関係を重視し、フォローした人の投稿が時系列で流れるシンプルなタイムラインを採用しています。
承認制コミュニティやブロック機能を備え、閉じた安心感のある空間を意識しています。
これは、かつてのmixiが持っていた「信頼できる仲間内のSNS」を再現する試みです。
「mixi」と「mixi2」の違い
| 観点 | mixi(初代) | mixi2 |
| 開始 | 2004年 | 2024年12月 |
| 参加方法 | 登録制(当初は招待制) | 完全招待制(18歳未満は不可) |
| アカウント互換 | あり(登録すれば利用可) | なし(別サービスとして独立) |
| 主な機能 | 日記、コミュニティ、足あと(廃止済)、ニュース | フォローTL(時系列)、発見タブ、コミュニティ、イベント、エモテキ、リアクション |
| コミュニケーション設計 | マイミク文化・コミュニティ掲示板中心 | 小規模コミュニティ+リアルタイム交流を重視 |
| 安全性 | 出会い系的利用でブランド毀損の経緯あり | 招待制と年齢制限で健全性を担保 |
今後の展望
mixi2はまだ招待制のためユーザー数は限定的ですが、広告のない静かなSNS体験を評価する声も増えています。
今後はPC版対応やマネタイズモデルの導入が予定されており、「SNS疲れ」したユーザー層や、かつてmixiを使っていた世代の“帰る場所”として注目が集まっています。
なぜmixiは衰退したのか?


かつて国内SNS市場を独占し、社会現象とまで呼ばれたmixi。しかし、その勢いは長くは続きませんでした。
ユーザー数は2010年前後をピークに頭打ちとなり、その後は急速に下降線をたどります。
栄光からわずか数年で、なぜここまで急激に存在感を失ったのか。
そこには、時代の変化に乗り遅れた点や、運営の判断ミス、そして競合サービスの台頭といった複数の要因が複雑に絡み合っていました。


スマホシフトの遅れ
2008年にiPhoneが日本に上陸し、スマートフォン時代が本格化しました。
しかしmixiはモバイル最適化やアプリ開発で出遅れ、PC中心の設計に依存していました。
その間にTwitterやFacebookはスマホ利用を前提とした体験を磨き、ユーザーがそちらへ流出していきます。
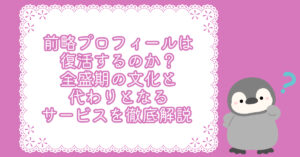
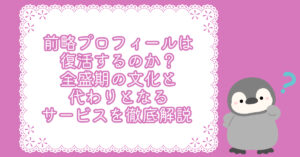
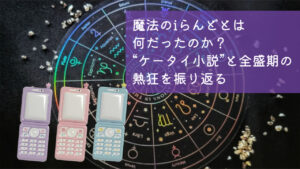
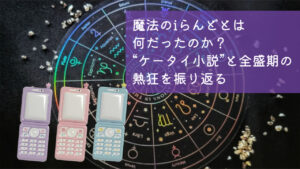
閉鎖的な招待制の強みが逆に足かせに
招待制は安心感をもたらした一方で、新規流入を制限する仕組みでもありました。
成長の天井を自ら低く設定してしまい、Facebookのように爆発的に拡大する機会を逃しました。


足あと廃止などの機能改悪
長年ユーザーに愛されていた足あと機能を2011年に廃止したことは、コミュニティ文化を根本から揺るがしました。
運営側は「プライバシー保護」を意図したものでしたが、多くの利用者にとってはmixiらしさが失われる出来事となり、大量離脱を招いた象徴的な転機でした。
出会い系イメージによるブランド毀損
健全な交流サービスだったはずが、次第に出会い目的や業者利用が目立ち、社会問題化する事件も発生しました。
これにより「安心して使えるSNS」という評価が揺らぎ、特に若年層や女性ユーザーが他サービスに移行するきっかけとなりました。
競合SNS(Twitter、Facebook、LINE)の台頭
2009年前後からTwitter、2010年代初頭にはFacebookが日本で急速に普及し、さらにLINEが登場しました。
短文投稿の即時性、実名ネットワークの信頼性、そしてチャット機能による気軽なコミュニケーション。それぞれがmixiにはなかった強みを提供し、ユーザーの利用時間を奪っていきました。
ミクシィ文化が残したもの


mixiは利用者数こそ大きく減少しましたが、その存在がインターネット文化に与えた影響は今も色濃く残っています。
足あとやコミュニティ、日記といった独自の仕組みは、単なる機能以上にユーザー同士の交流スタイルを形作り、後に登場したSNSの設計思想にも受け継がれていきました。
言い換えれば、mixiは日本における「SNS文化の基礎」を築いた存在だったのです。
コミュニティ文化の継承
mixiの「コミュニティ」は、趣味や属性ごとに人が集まれる仕組みでした。
現在ではFacebookグループやDiscordサーバーといった形で、その文化はしっかりと受け継がれています。
足あと文化と既読機能
「足あと機能」により、自分のページを誰が訪れたか分かる仕組みは独特でした。
いまではInstagramのストーリーズにおける「既読機能」が、その延長線上にあるといえます。
日記+コメントからタイムラインへ
mixi日記とコメントのやり取りは、現在のSNSにおける「タイムライン+リプライ」「投稿+コメント」の原型でした。
交流スタイルの礎を築いたといえます。
まとめ
かつて「SNSといえばmixi」と呼ばれた時代があったほどに、mixiはSNSの原点であり、現代ネット文化に確実な遺産を残しました。
しかし、様々な要因が重なり、mixiは一気に「SNS王者の座」から転げ落ち、結果として多くの人が「mixi 終了」と認識するほど、存在感は希薄化しました。
それでもmixiは完全には終わっておらず、2022年に実施された公式アンケートからは、一定数の利用者にとっては今も「居場所」であり続けていることがわかっています。
2024年末にリリースされた新SNS「mixi2」では、かつてのmixiのような「安心感のある小さなつながり」という原点を再構築しようとしています。
総じて言えるのは、mixiは“終了”ではなく“変容”を続けているということです。
栄光と挫折を経て、今もなお細く長く続くコミュニティ。その歴史は、日本のSNS黎明期を彩った遺産であり、同時に「次のSNSはどうあるべきか」という問いを投げかけていると言えます。
インターネットの変遷には、まだまだ語りきれない話がたくさんあります。
気になる方は、ほかのコラムも読んでみてください。


