禿同とは?ネットスラングの歴史と現在を徹底解説
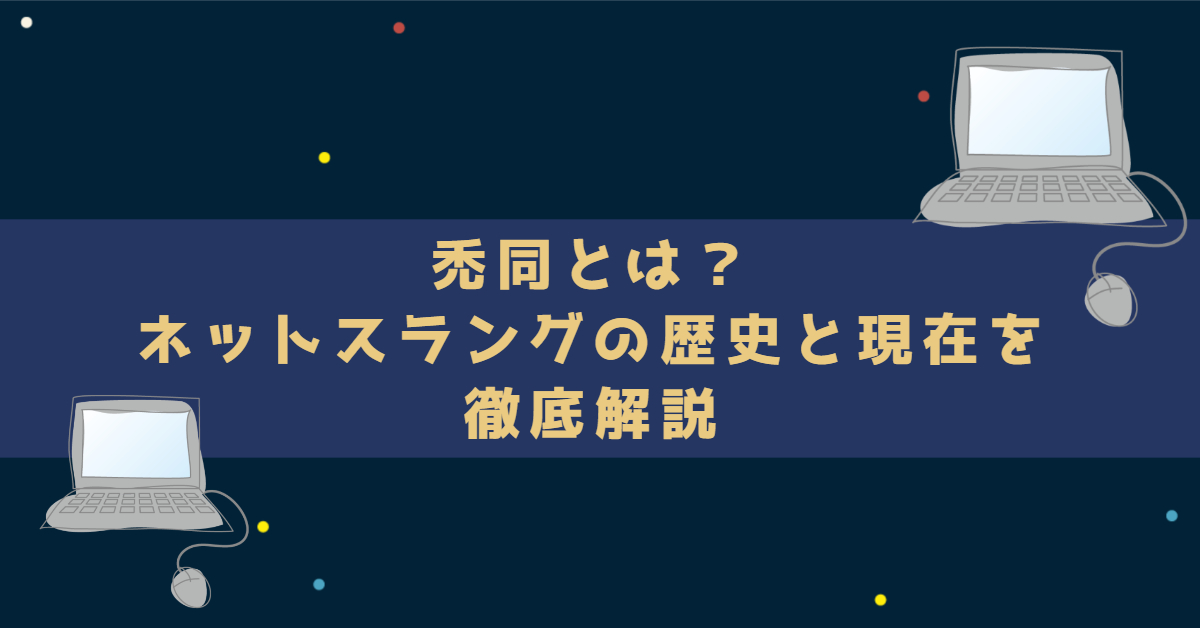
「禿同(はげどう)」という言葉をご存知でしょうか。
2000年代前半、匿名掲示板を中心に爆発的に広まり、誰もが気軽に使っていたネットスラングです。
しかし2025年現在、この言葉を日常的に使う人はほとんどいません。「死語」「古い」と言われ、若い世代には意味が通じないことも珍しくなくなりました。
今回は、禿同の意味や元ネタ、現代のスラング「それな」やSNSの「いいね」とのつながり、禿同というスラングが果たした文化的役割について解説します。
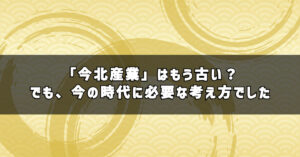
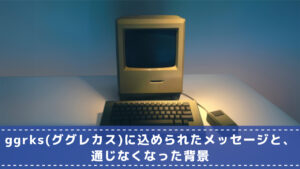
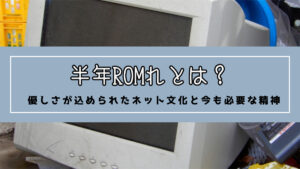
禿同の意味と読み方
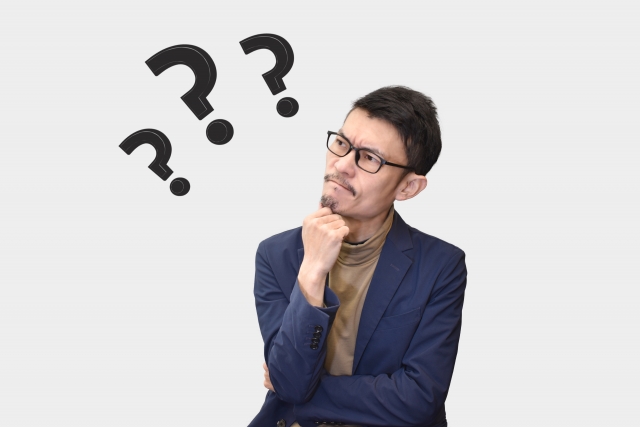
ネットスラングというものは、ぱっと見ただけでは意味が想像しづらいものが多いですよね。
「orz」や「乙」なども、初めて見た人には解読が難しかったでしょう。
「禿同」もそのひとつで、漢字をそのまま読むと「ハゲに同情?」と勘違いしてしまう人もいました。
当時の掲示板ユーザーにとって「禿同」は極めてポジティブで、強い共感を一言で表現できる便利な言葉だったのです。
読み方
「禿同」は はげどう と読みます。
意味
「激しく同意」の略語で、相手の発言に強く賛成する時に使われました。
つまり「完全にその通りだと思う」「超わかる」という感覚を表す言葉です。
A「夜中のカップラーメンって、なんであんなに旨いんだろうな」
B「禿同!」
禿同の元ネタと誕生の背景

「禿同」の元ネタは「激しく同意」→「激同」→「禿同」という流れです。
「激同」を「禿同」と誤変換したことから広まり、2ちゃんねる特有の「誤字もネタにする文化」がそれを定着させました。
名無しさん@お腹いっぱい。 2003/05/21(水) 22:11:04
激同って書こうとしたら禿同になったww
名無しさん@お腹いっぱい。 2003/05/21(水) 22:11:58
禿同ワロタw 流行らせようぜ
当時のネット文化は「打ち間違い」や「ネタ」がすぐに定着するスピード感がありました。禿同もその一例なのです。
禿同はいつ流行ったのか?

禿同が最も使われたのは2002年〜2007年頃。2ちゃんねるの勢いがピークに達していた時期です。
- ニュース速報板やVIP板では「禿同!」のレスが飛び交う
- mixiや魔法のiらんどの掲示板でも拡散
- 携帯小説の感想欄やブログコメントにも登場
タイトル:マックのポテトは神
1 :名無しさん :2004/11/30 23:50:12
マックのポテトに勝てるスナック菓子ある?
2 :名無しさん :2004/11/30 23:51:01
禿同
3 :名無しさん :2004/11/30 23:51:18
異論は認めない
4 :名無しさん :2004/11/30 23:52:44
禿同wwww
※ このブログは創業22年のWeb企業「セルバ」が運営しています。
興味があれば[会社紹介はこちら]もご覧ください。
禿同の使い方と返し方

ネットスラングは単語そのものよりも、どんな場面で、どんなノリで投げかけるかが重要です。
「禿同」は、掲示板の空気感を一瞬で共有できる“合図”のような役割を果たしていました。
当時の掲示板での具体的な使用例や、やり取りのなかで生まれたユーモラスな「返し方」について詳しく見ていきましょう。
基本の使い方
- 「禿同!」:強く賛成
- 「はげど」:軽い賛成、友達同士の会話向き
返し方
- 「禿同すぎて髪なくなるわw」
- 「禿同w でもちょっと違う」
12 :名無しさん :2005/07/18 21:02:11
夏は素麺が最強だな
13 :名無しさん :2005/07/18 21:02:25
禿同!
14 :名無しさん :2005/07/18 21:02:59
禿同しすぎてやばいww
禿同は死語なのか?

「禿同」は、なぜ「死語」と認識されるようになったのでしょうか。その理由をもう少し丁寧に見ていきましょう。
技術環境の変化
2000年代前半は、PCやフィーチャーフォンから掲示板にアクセスし、キーボードやテンキーで文字を打ち込むのが当たり前でした。
そのため、短縮表現やユーモアのある誤変換が自然に広がっていきました。
しかし、スマートフォンが普及して以降は、変換候補に「禿同」が表示されることはなく、文字入力よりも「ボタン一つで反応できる機能(いいね・スタンプ)」が主流となりました。
言葉そのものを入力する必然性が失われたのです。
コミュニケーション様式の変化
掲示板文化では「多数の人が匿名でコメントを重ねていく」ことが特徴でした。
そのなかで「禿同」は、相手の発言に瞬時に同調するサインとして非常に効率的に機能していました。
ところがTwitterやInstagramなどのSNSでは、発言に対して「いいね」や「リツイート」など視覚的・直接的な反応手段が整備され、わざわざ文字で「禿同」と書く意味が薄れてしまいました。
言葉の響きへの抵抗感
「禿同」という表記そのものも、広がりを妨げる要因でした。
漢字の「禿」は「ハゲ」を連想させ、ネガティブに受け止められることが多く、特に新しい世代にとっては「何が面白いの?」と感じられることが増えました。
結果的に、自然に淘汰されていったといえるでしょう。
はげどう?はげど?表記のバリエーション

- 「禿同」:正式(?)版
- 「はげどう」:ひらがな版、柔らかい印象
- 「はげど」:さらに省略したフランクな表記
禿同が古いと言われる理由

ネットスラングは、その時代の空気やテクノロジーと強く結びついています。
かつて勢いよく使われていた言葉も、環境や世代の変化によってあっという間に「古い」「死語」と呼ばれるようになるのです。
「禿同」も例外ではなく、いくつかの要因が重なって現在では過去の遺物のように扱われています。
ここでは、なぜ「禿同」が古いといわれるのかを、具体的な理由ごとに整理して見ていきましょう。
スマホ変換に出てこない
「禿同」はもともとPC掲示板文化で生まれた表現です。
しかしスマートフォンが主流になってからは、文字入力の自動変換に「禿同」が出てくることはほとんどありません。
つまり「入力のしやすさ」という観点から見ても、自然に使われなくなっていきました。
SNSの「いいね」やスタンプに役割を奪われた
2000年代は、文字レスポンスで同意を示すしかありませんでした。
しかしTwitterの「いいね」、LINEのスタンプ、Instagramの❤️など、ワンクリックで共感を示せる仕組みが普及したことで、わざわざ「禿同」と打つ必要性が消えました。
同意を示す表現は、より視覚的で簡潔な方向へ進化してしまったのです。
「はげ」という言葉のネガティブイメージ
「禿同」という漢字表記には「禿(はげ)」が含まれています。
これは当時のネットユーザーにはユーモラスに受け取られていましたが、幅広い世代に普及するには障害となりました。
特に若い世代にとっては「失礼なことを言って笑いを取る文化はもう古い」といった風潮が強まり、再定着することはありませんでした。
言葉遊び文化の変化
2ちゃんねる全盛期は「誤変換」や「打ち間違い」から新しい言葉を生み出す文化がありました。
藁(=笑)
逝ってよし
キターーーー!
しかし現代では、ミーム的拡散や画像・動画ネタが中心となっており、テキストだけのスラングは広がりにくい環境になっています。
世代間ギャップの拡大
30代以上にとって「禿同」は懐かしいフレーズですが、10代・20代前半にはほとんど浸透していません。
「意味を知らない=古い」「知られていない=使いづらい」という循環が起き、世代の入れ替わりとともに自然に淘汰されていきました。
ユーモアより効率が求められる時代
「禿同」には軽妙な笑いがありましたが、現代のSNSはスピード感と効率が優先されます。
わざわざ打つより「それな」「わかる」で済ませた方が伝わりやすい。またはスタンプやリアクションでワンタッチの方が合理的。
結果として「禿同」は“時代に合わなくなった表現”となりました。
禿同の文化的役割

「禿同」は単なるスラングにとどまらず、インターネット文化において独自の役割を果たしていました。
匿名掲示板という、顔も名前も出さない環境では「自分も同じ意見だ」と表明するだけでもハードルがあるものです。長文で語らずとも、一言「禿同」と書くだけで強い共感を示せることは、参加のしやすさを格段に高めました。
「匿名ゆえに孤独になりがちな場で、他者とのつながりを感じさせる役割」も担っていたと言えます。
膨大なスレッドのなかで、「自分と同じ気持ちの人がいる」と一目で分かることは、掲示板利用者に安心感を与えたのです。
また、「笑い」を伴う軽妙な響きも持っており、単なる同意表明以上の効果を持っていました。
掲示板の空気を和らげたり、同調する人たちの連帯感を強めたりする一種のユーモアでもあったのです。
現代SNSにおける「いいね」やスタンプと同じく、「共感を可視化する仕組み」として機能していたといえるでしょう。
単なる言葉遊びから生まれたにもかかわらず、インターネット上のコミュニケーションを円滑にし、共感を簡潔に可視化するという文化的意義を持っていたといえるでしょう。
まとめ
「禿同」は現在では死語と言っても過言ではありませんが、ネット文化史を語る上では欠かせない存在です。
共感を簡潔に表現するという点で、現代の「いいね」や「それな」と地続きになっています。
禿同はもう広く使われることはないかもしれません。しかし、それは単なる「古い言葉」ではなく、インターネットが共感の文化を育んだ証だと言えるでしょう。
インターネットの変遷には、まだまだ語りきれない話がたくさんあります。
気になる方は、ほかのコラムも読んでみてください。


