制作会社選びで迷っている方へ
費用相場・制作期間・進め方など、
まずは無料で方向性を一緒に整理いたします。
質問だけでも大歓迎です。
\ 強引な営業は一切ありませんのでご安心ください /


費用相場・制作期間・進め方など、
まずは無料で方向性を一緒に整理いたします。
質問だけでも大歓迎です。
\ 強引な営業は一切ありませんのでご安心ください /
現在、国内で多くの企業が直面している”システム老朽化”
あなたの企業では業務に支障がないからといって、つい後回しにしてしませんか?
しかしそのまま放置すると、ある日突然、誰も直せない・誰も仕組みを説明できない“ブラックボックス”と化したシステムが業務の足かせになる事態に陥るかもしれません。
本記事では、「システム老朽化とは?」という基本から、リスクと原因、そして見えにくい“ブラックボックス化”の怖さに焦点を当てながら、今すぐ取り組むべき対策について解説していきます。
「まだ動いているから大丈夫」と後回しにせず、ぜひこの機会に自社のIT環境を見直してみませんか?
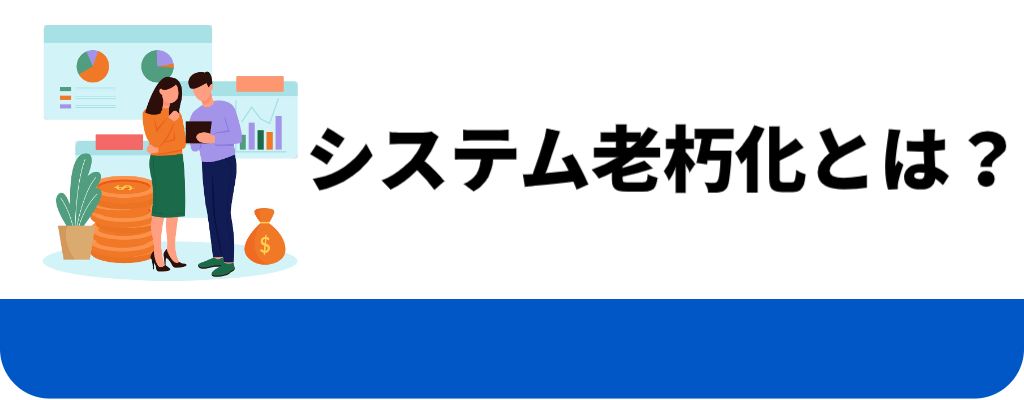
システム老朽化とは、企業の業務を支えるITシステムが長年にわたり使われ続け、技術面・運用面でさまざまな問題が表れてくる状態を指します。
具体的には、使用しているOSや開発言語のサポートが終了していたり、構成や機能が複雑化して誰も全体像を把握できなくなっていたりするケースが該当します。
当初は業務にフィットした仕組みであったとしても、10年、20年と長い年月が経つうちに、時代や働き方、技術の変化についていけなくなり、知らぬ間に大きなリスクとなっていることも少なくありません。
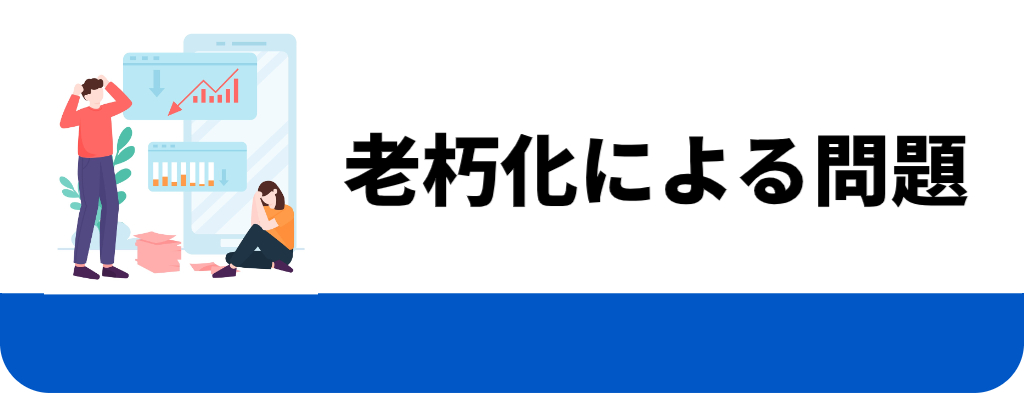
システムの老朽化のリスクは、技術的な問題だけではなく、セキュリティや業務効率、コストなどさまざまなリスクが潜んでいます。
老朽化によって起こりやすい代表的な問題を見ていきましょう。
老朽化システムではサポートが終了したソフトウェアやOS、開発言語が静養されていることがあります。
これらは、セキュリティパッチや脆弱性の修正などが行われておらず、セキュリティ面に問題を抱えています。
新しい業務フローに対応できないことや、UIが古く操作ミスが多くなること、検索や出力が遅いことや頻繁に起こるフリーズにより、作業に時間がかかり、社員のストレスにもつながります。
老朽化したシステムでは、対応できるエンジニア少なくなってしまうため、人数が限られてしまい、時間がかかってしまいます。
また、外部へ依頼する際には、主流な技術より費用が掛かってしまうため、時間と費用のどちらのコストも膨らんでしまいます。
老朽化システムでは、最新のクラウドサービスやツールと連携できないことが多くあります。
外部システムと連携ができなければ、新しい技術への開発が遅れることや、業務の自動化が進まないことにより、競争力や業務効率の低下を招く可能性があります。
このように、老朽化したシステムには見過ごせないリスクが多く潜んでいます。
まずは現状を見直し、できるところから対策を始めていくことが大切です。
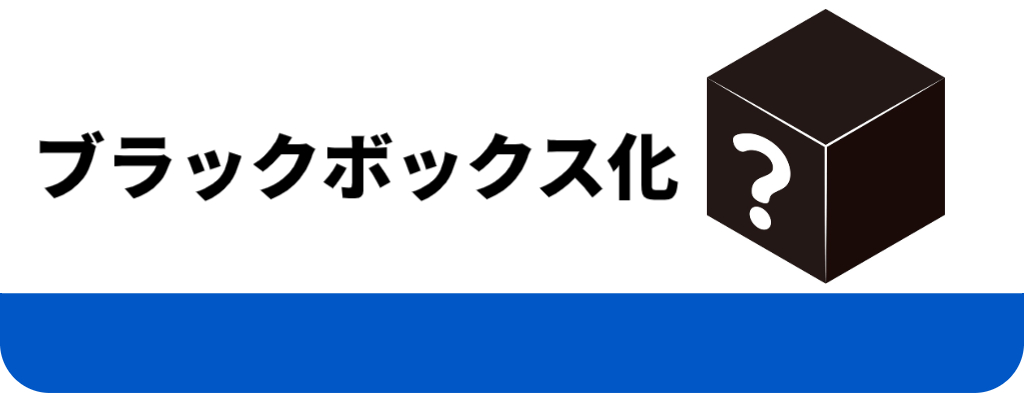
中でも特に警戒すべきなのが、「ブラックボックス化」です。
これは、システムの中身が誰にも分からなくなり、設計意図や処理内容、改修方法が不明な状態を指します。
担当者の退職や異動やマニュアルの不整備、改修によるシステムの複雑化、古い開発言語・技術などが原因で、システムのブラックボックス化が起きてしまいます。
セキュリティ問題では、対策が手厚い企業では、問題があまり深刻化しないことや、競争力の低下や、業務孤立なども、企業や業界によって大きな問題にならないこともあります。
しかし、ブラックボックス化は、他のリスクと違ってすべての企業に共通して起こり得る“普遍的な問題”であり、しかも気づかれにくく・後戻りしにくいという性質を持ちます。
ブラックボックス化が始まっていくと、システム改修の際に、大きな費用やリスク、時間を伴うようになってしまいす。
セキュリティや業務効率の問題は対策によってある程度抑えられますが、ブラックボックス化はシステムそのものの理解が失われるため、改修や移行すら困難になり、本質的な老朽化だと言えるでしょう。

老朽化は日々の業務の中で、少しづつ進行しています。
システムが老朽化する原因は、単に技術が古くなることだけではありません。次のような原因があります。
システムを担当していた社員が異動・退職し、引き継ぎが不十分なまま知見が失われるケースです。
外部ベンダーに依頼していた場合も、倒産や契約終了により技術が継承されず、ブラックボックス化が進むことがあります。
設計書や仕様書、運用フローといった技術的な記載がない、あるいは古いままというケースです。
開発当初にはドキュメントがあったが、改修の際に反映されず、現行のシステムとドキュメントに乖離が起きてしまうケースも少なくありません。
業務の変化やバグ対応の際に、その場しのぎのシステム改修を行い、システム全体の整合性が崩れるというケースです。
機能追加をしていくうちに、システムが複雑化し、修正のたびにリスクが増えていきます。
最終的には、改修が困難なシステムになってしまうこともあります。
現在は主流ではない古い技術や開発言語の使用により、改修や保守が困難になるケースです。
古い技術やシステムでは、サポート終了や、対応できる技術者が少なくなるといったケースは多くあります。
障害発生時の対応が遅れることや、移行ができなくなるなどで、老朽化が深刻化してしまいます。
現場からは「今すぐは困っていない」「改修に時間や費用がかかる」「担当業務が忙しい」といった声が上がり、老朽化対応は後回しにされがちです。
こうした”気づいていても動けない構造”もまた、問題を深刻化させる要因となります。

老朽化対応は、現場に丸投げするものではなく、経営視点からの明確な戦略が求められます。
ここでは、企業としてシステム老朽化にどう向き合い、どのように段階的に対応を進めていくべきかを解説します。
まずは、現行のシステムの問題を洗い出し、それぞれの状況を可視化します。
使用技術や改修履歴、担当部門・社員、現場での利用状況など把握していきます。
次に、可視化したシステムのリスクをそれぞれ評価し、それらに応じた対応方針を決めていきます。
システムの重要度と老朽化レベルによって優先順位をつけていきます。
システムによっては、新しい技術への移行や部分修正、もしくは、新しくシステムを作るという対応をとる必要もあります。
限られた予算や人員、時間の中で、効果的な改善を行うため、段階的なアプローチを行っていきます。
まずは重要度が高く、老朽化が進んでいるシステムから優先的に取り組んでいきましょう。
あわせて、スケジュールや社内体制の構築、関係者への共有や説明も同時に進めていきます。
安定なシステムの運用と、継続的な改善を行うための体制を作っていきます。
技術や業務は常に変化していくため、一度改善しても、老朽化は再び始まってしまいます。
定期的な見直しや、ドキュメント作成を習慣化し、普段の業務から改善点や課題を蓄積しておくことで、将来的なシステムの改修や運用に役立っていきます。
システム老朽化は現場だけでは解決できる問題ではなく、経営者と現場が連携し、戦略的に取り組むことで少しずつ改善していきます。
短期間で一気に解決は難しいので、優先度を明確にしたうえで、一歩ずつ着実に改善を進めていきましょう。
気づかないうちに老朽化が進行したシステムは、ある日突然「誰も触れない」「直せない」といった深刻な状態を引き起こします。
特にブラックボックス化したシステムは、放置すればするほどコストもリスクも高まり、対応が困難になります。
だからこそ、老朽化対応は「技術の問題」ではなく、経営戦略の一環として段階的に取り組むべき課題です。
現状を正しく把握し、優先度を明確にしたうえで、一歩ずつでも着実に改善を進めていくことで、コストを抑えながら効果的な改善をしていくことができます。