制作会社選びで迷っている方へ
費用相場・制作期間・進め方など、
まずは無料で方向性を一緒に整理いたします。
質問だけでも大歓迎です。
\ 強引な営業は一切ありませんのでご安心ください /

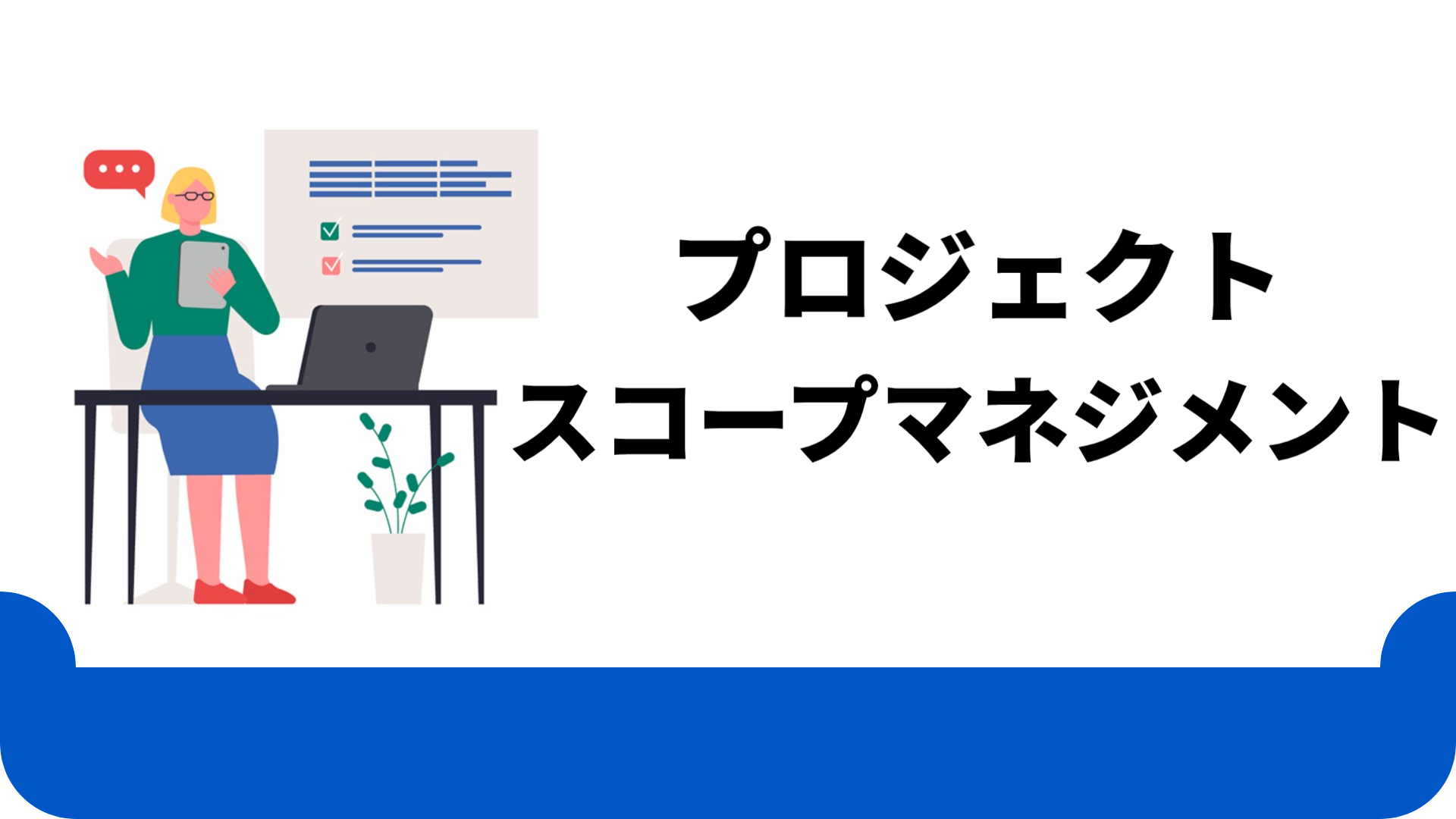
費用相場・制作期間・進め方など、
まずは無料で方向性を一緒に整理いたします。
質問だけでも大歓迎です。
\ 強引な営業は一切ありませんのでご安心ください /
システム開発のプロジェクトが失敗に終わる原因のひとつが、スコープ(作業範囲)の不明確さです。
成果物の仕様や作業範囲が曖昧だと、進行中に要求変更や作業追加が相次ぎ、納期・コスト・品質に大きな影響を与えてしまいます。
これらの多くは、計画段階で「何を作るか」と「どこまでやるか」を明確にしていないことが原因です。
本記事では、こうした失敗を防ぐための基礎知識から手法、ツールの選び方までを解説します。

成果物やスコープ(作業範囲)が曖昧なまま進行すると、追加要件が相次ぎ、納期の遅延やコストの増加が起きてしまいます。
「プロジェクトスコープマネジメント」とは、こうしたリスクを未然に防ぐために、プロジェクトの成果物や作業範囲を定義し、監視・管理する一連のプロセスです。
開始前には「何を・どこまで」行うのかを明確化し、その内容を全関係者に共有・合意を行っていきます。
その後の進行中は、変更要求を正式な手順で審査・承認し、定期的なレビューでスコープが計画通りかを確認します。
この一連のプロセスが、品質を高めつつ、納期・コストを安定的に守る基盤となります。
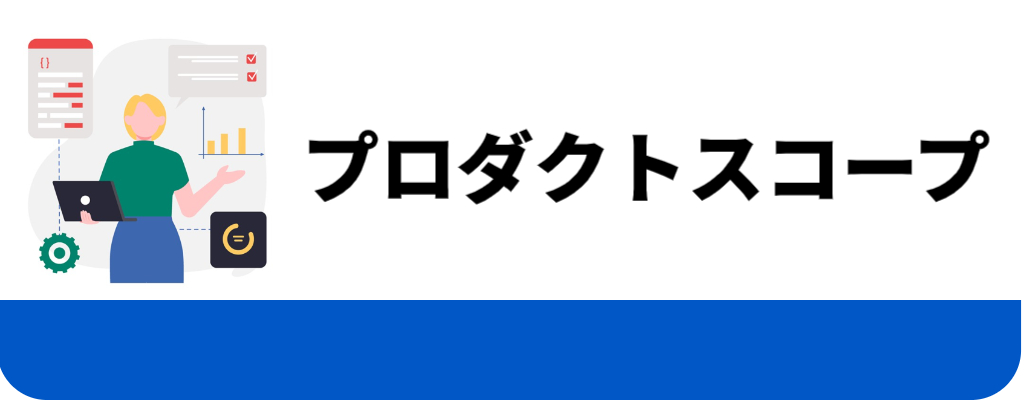
プロジェクトスコープを紹介する際によく聞かれる言葉で、「プロダクトスコープ」があります。
プロダクトは成果物を意味し、プロダクトスコープはその成果物の仕様・機能・品質を定めていくものです。
このプロダクトスコープはプロジェクトスコープの一部であり、成果物の姿を先に明確にすることで、必要な作業範囲を具体的に設定できます。
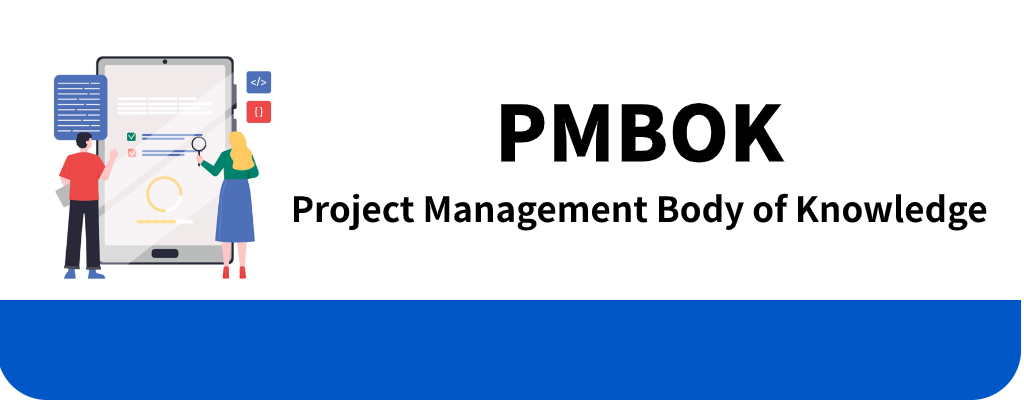
PMBOK(Project Management Body of Knowledge)は、米国に本部を置く非営利の専門団体であるPMI(Project Management Institute)が策定した、プロジェクトマネジメントの国際標準ガイドです。
計画、実行、監視・統制、終結といったプロジェクトの全工程を体系的に整理しており、契約条件として「PMBOKに準拠」と明記されるケースもあります。
世界中の企業や官公庁が参考にしており、プロジェクトの進め方や用語を統一するための基礎資料として利用されています。
PMBOKでは、プロジェクトマネジメントを10の「知識エリア」に分類しています。
その中のひとつであるプロジェクトスコープマネジメントは、プロジェクトで「何を作るのか」と「どこまで作業するのか」を明確にし、合意された範囲を計画・監視・統制するための領域です。
この領域には、スコープ計画の作成から要求収集、定義、WBS作成、妥当性確認、計画の監視・管理までが含まれます。
スケジュールやコスト管理の基盤を作るため、計画初期から着手される重要な領域です。
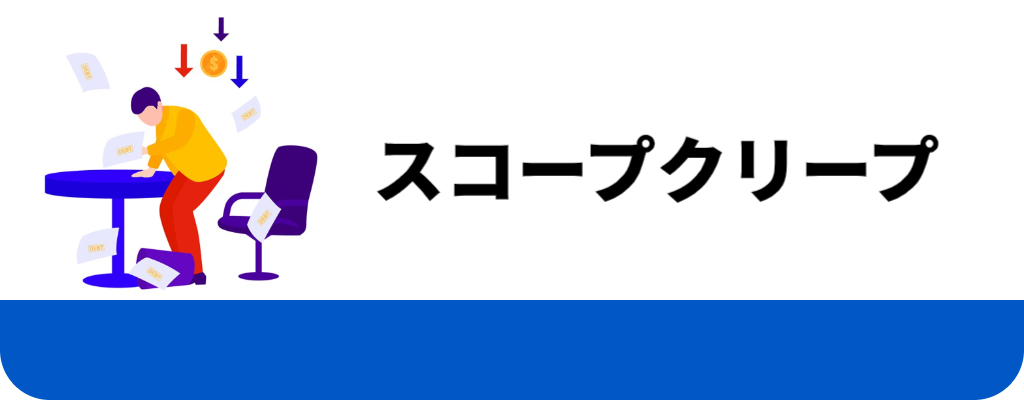
スコープクリープとは、プロジェクトの実行中に、当初合意した範囲を超えて作業や要件が少しずつ増えてしまう現象を指します。
小さな変更でも、積み重なれば納期遅延やコスト超過、品質低下を引き起こし、プロジェクト全体に悪影響を及ぼします。
ここでは、スコープクリープが発生する主な原因と、それを防ぐための対策を整理します。
これらの対策を計画段階から行うことで、スコープクリープの発生を事前に防ぎ、プロジェクトを安定して進行することができます。
作業範囲を明確に文書化し共有しなかったために、作業範囲を誤解して計画外の作業が増えてしまうケースです。
スコープ記述書に除外事項を記載し、関係者に共有する
関係者全員が成果物や作業範囲の認識をそろえられておらず、開発途中で要件変更が頻発するケースです。
初期段階ですべての関係者を巻き込み、要件定義書の合意をもらっておく
明確な変更承認フローがなく、口頭やチャットでの非公式な依頼がそのまま作業に組み込まれるケースです。
「変更要求書 → 影響分析 → 承認 → 実施」のような公式な変更管理プロセスを整備しておく

スコープクリープや認識のズレを防ぎ、プロジェクトを安定して進行させるためには、スコープマネジメントの工程を正しい順序で進めることが重要です。
ここでは、計画時に何を決め、実行時にどう管理し、完了時にどのように確認するのか、その流れを解説します。
成果物と作業範囲を、どのように定義・承認・監視・統制するかの方針を明確にする。
要件変更についてのルールを関係者に説明し、文書で承認を得る
関係者から、成果物や作業範囲に関する要望を聞き出し、記録する。
初期段階で必須・希望・低優先度に機能を分類する
収集した要求事項を整理し、プロジェクトで実際に対応する範囲を明確化した公式文書を作成する。
抽象表現は避け、具体的に記載する
スコープ記述書で定義した作業範囲を、管理可能な作業単位に階層構造で分解する。
担当者が1〜2週間で終えられるような管理しやすい単位まで細分化する
完成した成果物が、スコープ記述書で定義した範囲や品質基準を満たしているか、公式に承認を得る。
中間成果物でもレビューを行い、早期にズレを発見する
進行中の作業がスコープから逸脱していないかを管理する。
管理ツールを活用し変更履歴や進捗を可視化する
これらのステップとポイントを押さえて進行していくことで、スコープからの逸脱を防ぎ、納期・コスト・品質を安定して維持することができます。
工程ごとの合意と文書化を行うことで、プロジェクトの成功につながります。
プロジェクトスコープマネジメントは、計画から実行、そして監視・管理まで、プロジェクトの全期間を通してスコープを守り続けるための重要な活動です。
スコープを明確に定義し、その内容を関係者全員で合意し、各工程で必ず文書化して記録することで、スコープクリープや認識のズレを防ぐことができます。
プロジェクトの進行中は定期的なレビューや正式な変更管理プロセスを通じて、計画通りに進んでいるかを確認し、必要に応じて軌道修正を行います。
こうした取り組みを継続することが、納期・コスト・品質を安定させ、プロジェクト成功の確率を大きく高めるカギとなります。
システム開発のプロジェクト進行でお悩みの方は、お気軽にSELECTOまでご相談ください。
プロジェクトの進行や開発会社選びについて、システム開発歴20年以上のセルバがお手伝いします。