制作会社選びで迷っている方へ
費用相場・制作期間・進め方など、
まずは無料で方向性を一緒に整理いたします。
質問だけでも大歓迎です。
\ 強引な営業は一切ありませんのでご安心ください /

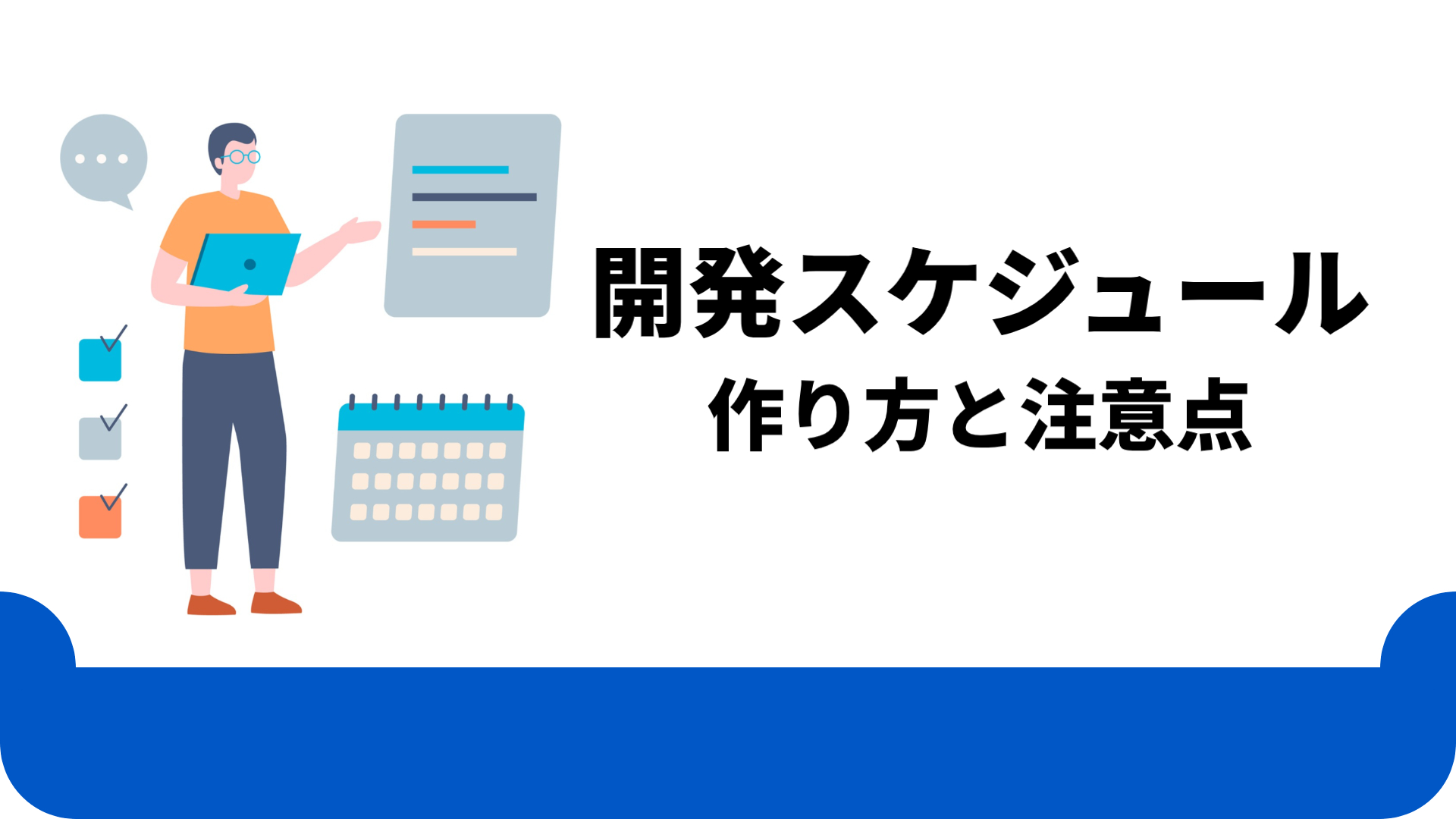
費用相場・制作期間・進め方など、
まずは無料で方向性を一緒に整理いたします。
質問だけでも大歓迎です。
\ 強引な営業は一切ありませんのでご安心ください /

開発って、どれくらいかかるの?



来月中にはリリースできますよね?
そんな風に、つい軽く見られがちなシステム開発のスケジュール。
でも実際には、要件定義から設計・実装・テスト・運用まで、明確な工程管理が必要不可欠です。
本記事では、開発スケジュールの基本的な構造や進め方、各工程の目安期間、そしてよくある失敗とその対策までをわかりやすく解説します。
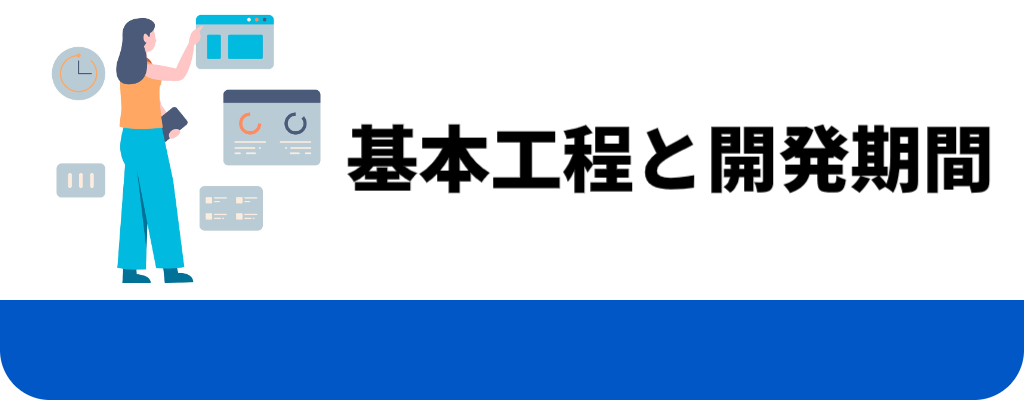
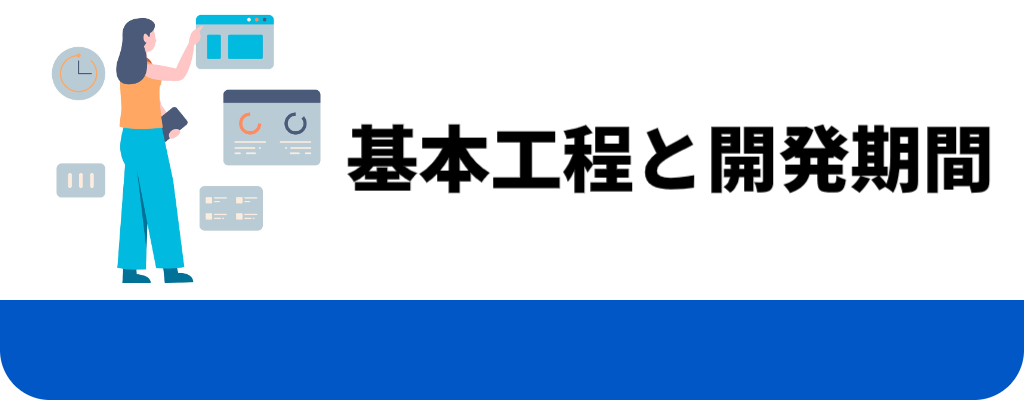
開発スケジュールを検討する上で、工程の流れを理解するだけでは不十分です。
実際には、各工程でどのような作業が行われ、どれくらいの時間を要するのかを具体的に把握しておくことが、現実的で破綻しないスケジュールを組むうえでの前提となります。
ここでは、ECサイトや予約管理システムなどの中規模開発プロジェクトを例に、工程別にどのような作業が行われ、どのくらいの期間を見込むべきかを整理していきます。
「どんなシステムを作るのか?」を明確にし、開発チームと発注側の認識を一致させる
要件定義で「何を作るか」をもとに、「どう作るか」を構造的に決める
基本設計で決めた大まかな構造をもとに、動作するための処理内容を細かく定義する
詳細設計書をもとに、実際にプログラムをコーディング(実装)する
実装したシステムが設計通りに動作するかどうかを検証し、バグや不具合を発見して修正する
完成したシステムを本番環境にリリースするための、運用準備など
システム開発には、想像以上に多くの時間がかかるものです。
開発チーム、発注者、業務部門など、関係者間で認識をすり合わせるため、要件の確認や合意形成だけでも相応の時間を要します。
また、システムは一度作り始めると手戻りが大きなコストにつながるため、設計段階で画面構成や処理内容、外部連携などをできるだけ具体的に詰めておく必要があります。
さらに、不具合修正や承認・レビュー待ちなど、実装以外にも時間を要する工程が多数存在します。
こうした工程は、小規模な案件でも大規模な案件でも本質的には共通です。
もちろん、規模が大きくなれば実作業にかかる期間は延びますが、各工程にかかる「相対的な比率」は大きく変わらないことが多いです。
そのため、システム開発にはあらかじめ一定以上の期間を見込んでおくことが前提となるのです。


スケジュールを考えるうえでは、「どの開発手法で進めるか」も重要な判断材料になります。
ここでは、代表的な手法である「ウォーターフォール」と「アジャイル」の違いについて簡単にご紹介します。
ウォーターフォール開発とは、工程を上から下へ水が流れるように順番に進めていく開発手法です。
各工程を一つずつ完了させてから進めていく、直線的で計画重視の進め方です。
アジャイル開発の「アジャイル」とは、英語で“俊敏”や“柔軟”を意味する agile という単語に由来しています。
その名の通り、アジャイル開発は変化に柔軟に対応しながら、小さな単位で反復的に開発を進めていく手法です。
要件や仕様をすべて最初に固めるのではなく、短い期間ごとに設計・実装・テストを繰り返し、ユーザーのフィードバックを反映させながら完成に近づけていくのが特徴です。
| 比較対象 | ウォーターフォール | アジャイル | ||
|---|---|---|---|---|
| 向いている案件 | 要件が明確で、関係者が多い案件 | 要件を変更し、改善していく案件 | ||
| コミュニケーション | 文書ベースの報告型 | 対話ベースの共有型 | ||
| 柔軟性 | 変更に弱く、再見積もりが必要 | 柔軟に対応可能 | ||
| スケジュール設計 | 設計しやすい | 設計しにくい | ||
ウォーターフォール型は、スケジュールを事前に設計しやすく、決められたものを正確に作る力に優れています。
関係者が多く、規模の大きい開発に向いていますが、変更に弱く手戻りのコストが大きいのが難点です。
一方アジャイル開発は、要件変更に柔軟で、ユーザーの声を反映しながら進められるのが特長です。
Webサービスやスピード重視の案件に適していますが、スケジュールやコストの見通しが立てにくいという側面もあります。
ただし、両者で開発期間そのものが大きく変わることは少なく、違いが出るのは「進め方」と「管理のしやすさ」です。重要なのは、プロジェクトの特性に応じて、適切な手法を選ぶことです。


システム開発において、スケジュール通りにプロジェクトが完了することは想像以上に難しいものです。
技術力や作業量だけでなく、関係者との調整や不確定要素への対応といった「計画外の要因」が日程に大きく影響します。
ここででは、スケジュールを立てるうえで押さえておくべき基本の流れと、実際の現場で起こりがちな落とし穴についてわかりやすく解説します。
要件定義で明確になった機能や業務フローをもとに、作業を細かく分解し、「誰が・何を・いつまでにやるか」を構造化していきます。
これがWBS(Work Breakdown Structure)です。スケジュール・工数見積もり・進捗管理のすべての土台となります。
作業ごとに「このタスクは何時間・何日かかるか」を見積もります。
このフェーズでの精度がスケジュール全体の現実性を決定づけるため、甘く見積もるのは禁物です。
工数(日数)をカレンダー上に展開し、実際のプロジェクト期間として落とし込むフェーズです。
ここで、「いつ・誰が・何を・何日間で」行うのかを視覚化します。
スケジュールを関係者に提示し、実行可能かどうかのフィードバックをもらいます。
ここでの合意形成を省略すると、後から炎上するリスクが高くなります。
スケジュール作成は、単なる作業の並べ替えではなく、プロジェクト全体を成功に導くための「戦略づくり」です。
メンバーの稼働状況や社内フロー、要件の不確実性など、細かな部分に目を配ることが、後の手戻りや炎上を防ぐカギになります。


システム開発では、どれだけ丁寧に計画を立てても、スケジュールが遅れる要因は必ず潜んでいます。
ここでは、よくある遅延の原因と、それぞれに対する現実的な対策を紹介します。
要件定義の段階で内容が曖昧なまま進んでしまうと、後になって「イメージと違う」「あの画面がない」「使いにくい」などの問題が発覚します。
一度進んだ工程を戻ることになり、再設計・再開発・再テストと、余計な時間がどんどん積み重なっていきます。
実装が完了したあと、結合テストや総合テストで大量のバグや仕様ミスが発覚することで、修正や再テストに時間がかかり、スケジュールが後ろにずれ込むケースです。
特に「単体テストが甘い」「設計のままテスト仕様が書かれていない」といった場合に多く発生します。
プロジェクト開始時に、ぎりぎりの工期でスケジュールを立ててしまうと、わずかな遅れや仕様の追加があっただけでスケジュールが崩れる可能性があります。
「前工程が1日でも遅れると後ろが全部押す」という状況は、余裕のない設計が原因です。
スケジュール遅延は、特別なトラブルではなく、ちょっとした準備不足や見落としから始まることがほとんどです。
だからこそ、あらかじめリスクを想定し、工程ごとに余裕をもたせたスケジュール設計を意識することで、防げる遅延を確実に減らすことができます。
システム開発のスケジュールは、単に日付を並べるだけの作業ではありません。
要件定義から設計・開発・テスト・リリースまで、それぞれの工程に適切な時間と判断の余白を確保することで、計画の実現可能性が高まります。
紹介した手順や注意点を踏まえて、無理のない、現実的なスケジュール設計を心がけることで、プロジェクトの炎上を防ぐことができます。