制作会社選びで迷っている方へ
費用相場・制作期間・進め方など、
まずは無料で方向性を一緒に整理いたします。
質問だけでも大歓迎です。
\ 強引な営業は一切ありませんのでご安心ください /


費用相場・制作期間・進め方など、
まずは無料で方向性を一緒に整理いたします。
質問だけでも大歓迎です。
\ 強引な営業は一切ありませんのでご安心ください /
会社で使っている業務システムやWebサービスが、毎日あたりまえのように動いているのはなぜでしょうか?
実はその裏側では、目立たないけれど非常に重要な「システム運用」という仕事が行われています。
サーバーやネットワークの監視、障害時の復旧対応、データのバックアップ。こうした日々の運用がなければ、システムはすぐにトラブルを起こし、業務が止まってしまいます。
本記事では、「そもそもシステム運用とは何か?」という基本から、目的・役割・業務内容、運用方法の選び方、さらには属人化リスクへの対策までを、初心者にもわかりやすく丁寧に解説していきます。

システム運用とは、企業や組織で導入されているITシステム(サーバー・ネットワーク・ソフトウェアなど)を、安定して継続的に稼働させるための管理・対応業務全般を指します。
たとえば、企業のWebサイトや業務システム、顧客管理システムなどが止まってしまうと、大きな損失が発生します。
システム運用は他にも目的があり、障害やトラブルを未然に防ぐこと、セキュリティを維持することなども業務に含まれています。
システム運用は、障害を未然に防ぎ、トラブル時には迅速に復旧する「縁の下の力持ち」のような存在です。

システム運用は、しばしば「保守」と混同されることがあります。
実際、両者はシステム開発の工程においても隣接しており、業務内容にも共通点があるため、違いが見えにくいかもしれません。
しかし、運用と保守は目的も役割も異なるものです。この2つの業務の違いについて、わかりやすく整理します。
| 比較項目 | 運用 | 保守 | ||
|---|---|---|---|---|
| 役割 | システムの安定稼働 | システムの不具合修正と改善 | ||
| 目的 | 業務を安全に継続する状態の維持 | 動作の安定性の維持と向上 | ||
| 主な業務内容 | サーバーやネットワークの監視 | バグ修正やコード改修 | ||
| 業務のタイミング | システムの稼働中は常に(定期的) | 障害報告、バグの発見時(不定期) | ||
このように、運用と保守は、目的も業務内容も異なる性質を持っています。
まず運用は、システムの安定稼働を行い、業務を安全に継続する状態の維持を目的としています。
業務内容としては、サーバーやネットワークの監視以外をはじめ、アカウントや操作ログの管理、バックアップ、パッチ適用、システム障害の一次対応(状況確認、再起動、関係者への連絡など)などが挙げられます。
そのため、運用業務は、システムの稼働中は継続的に行われるため、「定常業務」といえます。
一方で保守は、システムの不具合修正と改善を行い、システム動作の安定性を維持し、向上させる目的があります。
具体的な業務内容には、バグ修正やコード改修に加え、パフォーマンスの向上、仕様変更時に伴う設計書や仕様書の更新、ライブラリのアップデートなどを行います。
そのため、保守業務は、障害や不具合、性能低下、仕様変更などが発生した際に行われるため、突発的な「対応業務」といえます。
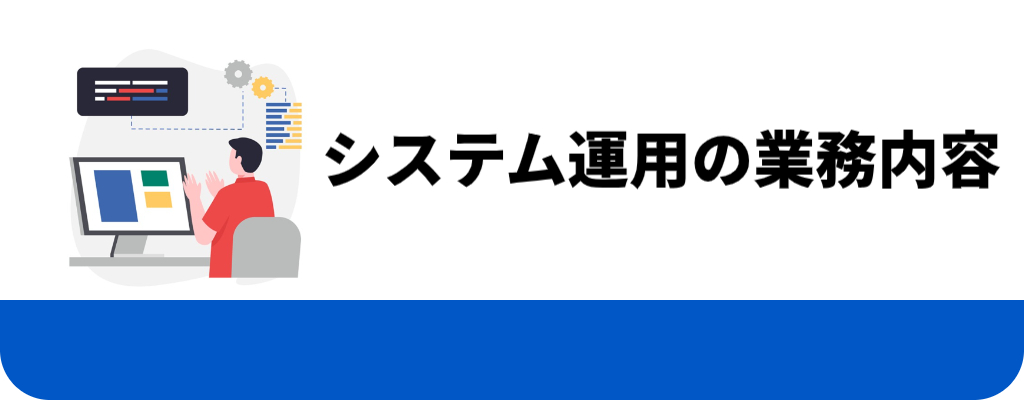
システム運用の目的が「業務を安全に継続する状態の維持」であることはおわかりいただけたかと思います。
では、その目的を達成するために、どのような業務を行ってきているのでしょうか?ここでは、システム運用の具体的な業務内容についてご紹介します。
システム運用において最も基本であるのが、「監視業務」です。
これは、サーバーやネットワーク、アプリケーションが正常に動作し続けているかどうかを常にチェックする業務です。
システムはいつ、どんなタイミングで異常が起こるかわかりません。
だからこそ、サービスが動いているかを確認する「死活監視」や、CPUやメモリ使用率などの状態を把握する「リソース監視」が欠かせないのです。
こうした監視によって、業務停止や処理遅延といった重大なトラブルを事前に防ぐことができます。
多くの場合、障害の前には何らかの兆候が現れます。それにいち早く気づくことが、システムの安全稼働を守るための第一歩です。
アカウント管理とログ管理は、システム運用における「セキュリティ維持」と「トラブル対応」の要であるといえます。
誰が、いつ、どんな操作を行ったかを把握することで、不正アクセスや情報漏洩の防止、障害時の調査に役立ちます。
アカウント管理では、新入社員や異動者のアカウント発行や権限設定、退職者や休職者のアカウント削除・停止、アクセス権限の見直しを行うことで、セキュリティを維持しています。
ログ管理では、ユーザーのアクセスや操作、システムのエラーや認証のログ(履歴)を管理・分析していきます。
どんなに堅牢なシステムを構築しても、トラブルがゼロになることはありません。
システム運用においてバックアップ業務は、「最後の砦」になるもので、最も重要なリスク対策のひとつです。
定期的にデータを保存・複製し、トラブル発生時に元の状態へ戻せる体制を整えておきます。
ただバックアップするのではなく、保存先を分散させることや、データの復元をテストすること、定期的な自動バックアップの設定を行うことで、より信頼性の高いバックアップ運用が可能になります。
システム運用の現場では、「障害が発生した直後にどう動くか」が非常に重要です。
この初動対応を「一次対応」と呼びます。
以下が、障害時の一次対応の基本ステップです。
監視ツールやユーザーからの問い合わせで障害を認識
障害が起きた時間、監視ツールで障害の内容と範囲の確認
再起動やサーバの一次停止を行い、影響を抑える
障害の確認と応急処置が終わり次第、開発・保守チーム、マネジメント層などに連絡と共有を行う
日時や障害の内容、応急処置、連絡内容や連絡先を記録に残し、関係者に報告する
一次対応の目的は、被害の拡大を防ぎ、必要な情報を集め、次の対応へ正確に引き継ぐことです。
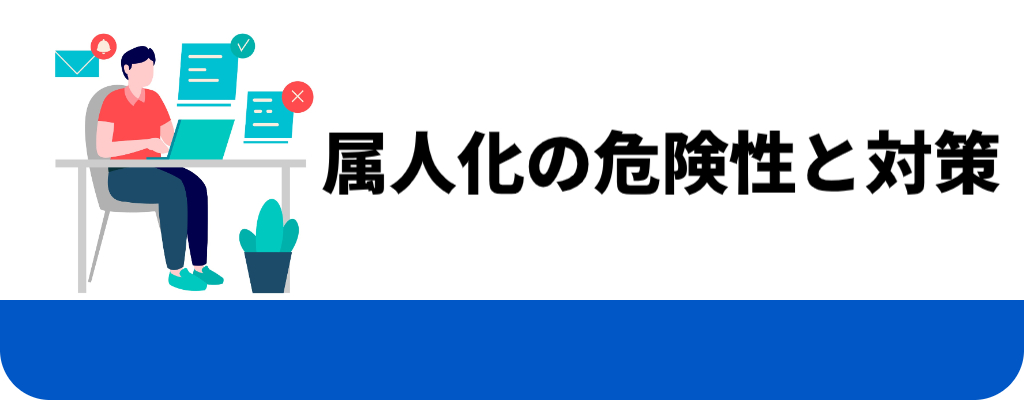
システム運用において「属人化」はしばしば問題となります。
属人化とは、ある業務やノウハウが特定の担当者にしかわからない状態になっていることを指します。
担当者の退職や異動により、運用に大きな影響を与えてしまうため、システムの安定性・継続性という観点からは、非常に危険な状態にあるといえます。
属人化の主な原因が見えてきたところで、次に気になるのは「どう防げばいいのか」という点ではないでしょうか。
ここからは、システム運用の現場で実践できる属人化対策を、具体的に紹介していきます。
属人化の最も根本的な原因は、「やり方が頭の中にしかない」ことです。
そこで重要なのが、マニュアル・手順書を整備しやり方を明文化することです。
スクリーンショットを使い、操作手順や判断基準・注意点を明記しましょう。
同じ人が同じ業務を担当し続けると、知識や経験が個人に偏ってしまいます。
業務をローテーションしていくことで、属人化を防ぐことができます。
個人の知識や経験は、共有しなければ、「無い」のと同じです。
作業報告書や日誌、ミーティングなどで業務の情報を「溜める」のではなく、「流す」ような構造作りをしましょう。
属人化は、「この人しか知らない」という記憶依存によって始まります。
これを防ぐには、作業内容や対応履歴を自動的に記録し、誰でも確認できる状態にしておくことが大切です。
定期的な作業は可能な限りスクリプトやツールで自動化し、実行結果や操作ログは自動で保存・可視化できる仕組みを整えましょう。
また、設定変更やファイル修正などもバージョン管理ツールを活用して履歴を残すことで、後から誰が何をしたかが明確になります。
記録されていることで、運用の属人化を防ぎ、透明性を持たせることが可能になります。

現在のシステム運用では、「オンプレミス」と「クラウド」という2つの方法が主流となっています。
自社でハードウェアを持ち、構成や運用を自由に管理できるオンプレミス。
一方で、柔軟性とスピードを重視し、運用負荷を軽減できるクラウド。
いずれを選ぶかは、業務要件・セキュリティポリシー・予算などによって変わってきます。
ここでは、この2つの運用方法の特徴と使い分けのポイントを整理します。
| 比較項目 | オンプレミス運用 | クラウド運用 | ||
|---|---|---|---|---|
| 運用場所 | 自主 | 外部クラウドサービス | ||
| 運用者 | 自社の担当者、チーム | 自社のクラウド担当者 | ||
| 初期コスト | 高い | 低い | ||
| 運用コスト | 高い | 中程度 | ||
| 柔軟性 | 低い | 高い | ||
| 拡張性 | かなり高い | 高い | ||
| セキュリティ | かなり高い | 高い | ||
オンプレミス運用とは、サーバーやネットワーク機器などのインフラを自社で保有・管理し、構築・運用する方式です。
企業内に物理的な設備を設け、自社スタッフまたは専任チームがシステムを管理・運用します。
この運用方法はカスタマイズ性に優れ、特殊なシステムや要件にも柔軟に対応できます。そのため、長期的な安定運用に適しています。
また、社内でデータや機密情報を完結して管理できる点から、セキュリティや法規制が厳しい業界では現在も多く採用されています。
一方で、デメリットとしては次のような点が挙げられます。
自由度と制御性は高いものの、コストと運用負担が大きい運用方式です。
クラウド運用とは、AWS・Microsoft Azure・Google Cloud Platform(GCP)などのクラウドサービスを利用して、
インフラやシステムをインターネット上で構築・運用する方法です。
オンプレミスのように自社でハードウェアを保有せず、使いたいときに使いたい分だけ利用できるのが大きな特徴です。
そのため、初期費用を大幅に抑えられ、短期間で導入できるというメリットがあります。
さらに、クラウドはリソースの拡張・縮小が簡単に行えるほか、データを分散して保存できるため、地震や火災、停電といった災害対策にも強いという特長があります。
ただし、クラウド運用にもいくつか注意点があります。
クラウド運用はスピードと柔軟性に優れた現代的な方法である一方、正しい設計と管理が求められる選択肢です。
ちなみに、オンプレミス運用とクラウド運用は「システムをどこに置くか」という観点でよく比較されますが、
実際には「誰が運用するか」という視点も同じくらい重要です。
自社内での対応が難しいケースに備えて、運用業務の一部またはすべてを外部の専門業者に委託する「外部依頼(アウトソーシング)」を採用する企業も増えています。
監視・障害対応・バックアップ確認など、日常的な運用をプロに任せることで、社内の負担を軽減しながら安定した体制を維持できるというメリットがあります。
システム運用は、日々の業務の安定と継続を支える、まさに「縁の下の力持ち」です。
障害対応や監視だけでなく、情報管理、バックアップ、属人化対策、運用方式の選定まで、幅広い視点が求められます。
オンプレミス、クラウド、外部委託といった運用方法を理解し、自社に合った体制を選ぶことが、安定した業務運用の第一歩になります。
システム運用の外部依頼(アウトソーシング)などを検討されている方は、お気軽にSELECTOまでご相談ください。
最適な開発会社を提案させていただきます。