制作会社選びで迷っている方へ
費用相場・制作期間・進め方など、
まずは無料で方向性を一緒に整理いたします。
質問だけでも大歓迎です。
\ 強引な営業は一切ありませんのでご安心ください /


費用相場・制作期間・進め方など、
まずは無料で方向性を一緒に整理いたします。
質問だけでも大歓迎です。
\ 強引な営業は一切ありませんのでご安心ください /

自分がもっと早く気づいていれば……。
そう後悔するプロジェクトマネージャーは少なくありません。
一方で、このような無力感を抱く若手も多いでしょう。



自分はまだ新人だから、何もできない……。
そうして誰も止められないまま、プロジェクトは静かに炎上へと向かっていきます。
しかし、プロジェクト炎上の多くは大きな失敗ではなく、小さな違和感が積み重なった結果が表面化したものがほとんどです。
この記事では、マネージャーと新人がともに理解しておくべき炎上の本質と、それぞれにできる行動を明らかにします。


「プロジェクト炎上」とは、進行中のプロジェクトが計画通りに進まず、納期・品質・コスト・人員が同時に破綻するレベルの危機的状態でのことを指します。
特にITやシステム開発の現場でよく使われる言葉ですが、実は業種を問わず、チームで何かを成し遂げようとする場面ならどこでも起こり得る現象です。
一見すると、プロジェクトは順調そうに進んでいるように見えても、実際にはチームが疲弊し、成果物の質も低下。気づいた時には、引き返すことのできない状態になっているケースも少なくありません。


プロジェクトが炎上する原因は、決して「誰かのミス」だけではありません。
実は、初期段階から仕組みとして組み込まれてしまっている構造的な問題が影響していることも多いのです。
ここでは、現場でよく見られる具体的な原因と、それらの背後にある構造的な落とし穴や、ミスが起きやすくなる背景について解説します。
プロジェクト炎上の典型的な原因のひとつが、要件定義の曖昧さです。
「何を・どこまで作るか」が明確に合意・文書化されていないと、認識のズレから手戻りや仕様変更が何度も発生します。
顧客の要望がうまく言語化されていない場合も多く、形式的なヒアリングでは意図を正確にくみ取ることは難しいです。
特に、要件定義に十分な時間が取れないプロジェクトや、アジャイル型の進行では、初期の曖昧さが後半の混乱を招きやすくなります。
顧客・営業・開発など、プロジェクト関係者のあいだで成果物の完成イメージが共有できていないことも、よくある炎上の原因の一つです。
情報共有や技術理解のレベルに差があることで、現場では想定以上の負荷や難易度が発生しやすくなります。
デザインやUIのイメージが共有されないまま開発が進むと、フィードバックのタイミングを逃し、要件変更も困難になります。
こうした状態を放置すると、「期待していたものと違う」といった不満が噴出し、手戻りの連続から炎上に発展してしまいます。
当然ながら、仕様変更が頻繁に発生すると、開発チームに負担が集中します。
すでに完了した設計やテストをやり直す「手戻り」が発生し、工数が増加。加えて、スケジュールの再調整や進行計画の見直しも必要になります。
このような変更が立て続けに起きると、開発現場が対応しきれなくなり、最終的には予算の膨張や品質の低下といった深刻な問題へとつながってしまいます。
余裕のないスケジュール設定でも、それ自体が即座に問題を引き起こすわけではありません。
しかし、スケジュールが理想通りに進む前提で組まれていると、わずかな遅れや仕様変更が発生しただけで、プロジェクト全体に大きな影響を及ぼします。
トラブルが途中で発生した場合、特にテストやリリース準備といった校本の工程を削って調整せざるを得なくなり、結果的に品質の低下を招くことになります。
限られた時間の中でプロジェクトを進行させようとすれば、開発チームに大きなプレッシャーがかかり、過度な残業や休日対応が発生する要因にもなります。
その結果、集中力やモチベーションの低下を引き起こし、チーム全体のパフォーマンス悪化につながるリスクも高まります。
プロジェクトを進行するうえで、見落とされがちな人的リスクが「属人化」と「スキルミスマッチ」です。
属人化とは、特定のメンバーだけが業務や技術を把握しており、その人しか対応できない状態を指します。
担当者が不在になると業務が止まり、周囲もサポートできず、ブラックボックス化が進行してしまいます。
一方、スキルミスマッチとは、担当者のスキルや経験がプロジェクトの要求に見合っていない状態です。
難易度の高い作業を任されても対応しきれず、品質の低下や手戻りの連鎖につながるリスクがあります。
これらのように、プロジェクトが炎上する背景には、誰か一人のミスではなく、構造的な問題や、見過ごされがちな人的リスクが潜んでいることが少なくありません。
一見すると小さな綻びでも、放置すれば連鎖的にトラブルを引き起こし、やがてプロジェクト全体に大きな影響を与えてしまいます。
設計・体制・チーム運営のすべてにおいて、炎上の芽を早期に見つけて潰せるようなプロジェクト設計が求められます。
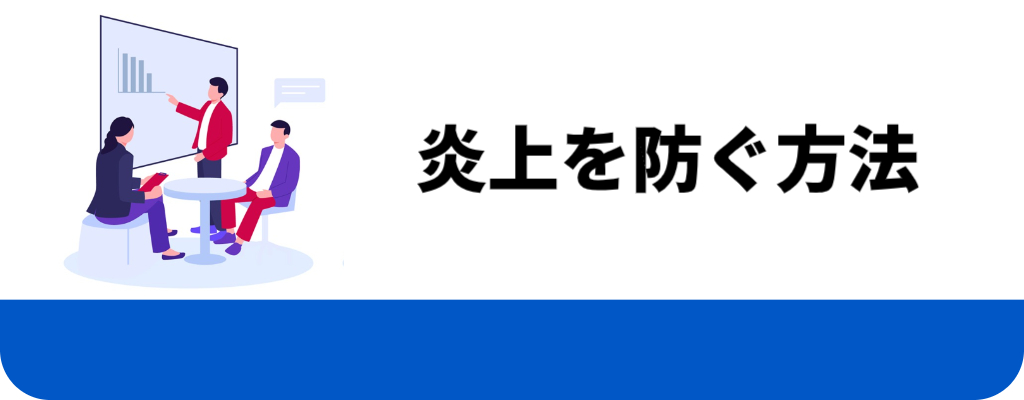
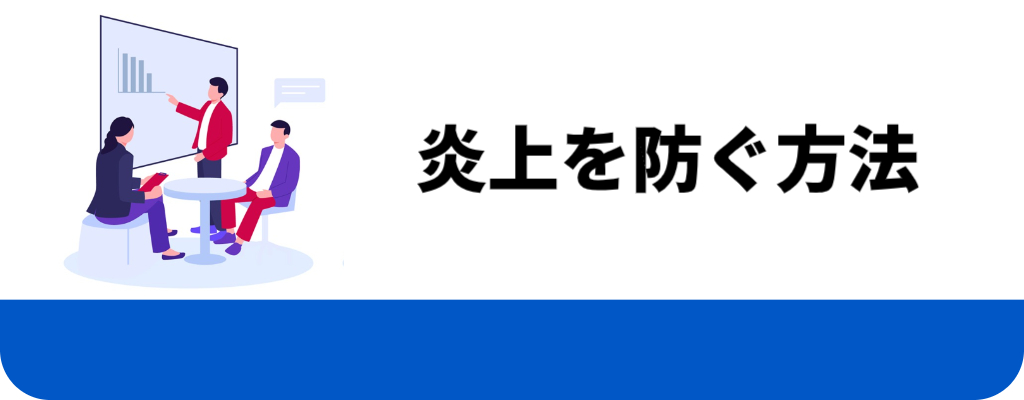
炎上を完全にゼロにすることは難しいですが、「構造的な問題」を減らしていくことで、長期に兆候を察知し、対処ができる体制を整えておくことで、炎上をある程度防ぐことができます。
ここでは、炎上を未然に防ぐためのポイントをご紹介します。
要件が曖昧なまま進めると、後から「こんなはずじゃなかった」と手戻りや対立が起こります。
開発側・顧客側の間で、機能や画面の完成イメージを事前にすり合わせ、文書と図で明文化しておくことが重要です。
スケジュールは「理想」を前提に組むのではなく、「多少の遅れは起きるもの」という前提で設計するべきです。
工程ごとの予備日や、想定外の作業を吸収する余裕がないと、ひとつの遅延が全体に影響して炎上につながります。
開発中の仕様変更はよくあることですが、ルールや合意なしに受け続けると、作業範囲が膨張しプロジェクトが崩れてしまいます。
変更が発生した際は、影響範囲の確認・納期やコストの再調整・記録と合意をセットで管理することが基本です。
炎上は、ひとつの大きなミスよりも、小さな見落としや放置された違和感の積み重ねで起こります。
「ちょっと変だな」「伝わってないかも」と思った瞬間に、遠慮せず言葉にして共有する文化が、初期消火につながります。


メンバーや新人が感じた違和感を拾えるかどうかは、プロジェクトの進行性に直結します。
現場では声が上がらず、安定しているように見えても、プロジェクトが炎上に向かっている可能性があります。
何が問題で、なぜ共有されないのか。その背景には、組織文化と社内構造が深く関係しています。
成果主義的は競争を生み、個人のモチベーションを高める一方、ミスやトラブルは原点対象という評価軸が強すぎると、「失敗を見せると損」という空気が現場に流れるようになります。
また、成果主義的な文化は「結果」が見られがちで、途中の試行錯誤や違和感といったプロセス上での気づきが軽視される傾向にあります。
そのため、メンバーは「言っても評価されない」や「言わずに黙ってやるほうが印象が良い」と感じ、報告や相談を控えるようになってしまいます。
これを防ぐために、プロセスでの行動を評価対象にしていくことや、「相談してくれて助かった」とポジティブなリアクションを返すことで、成果主義と心理的安全性を保つことができます。
報告や相談が起きないのは、心理的な問題だけではありません。
いうべき問題があっても、「いつ・どこで・誰に」言えばいいのかわからないという場合、報告や相談できる場がないことが、沈黙の原因になっている可能性があります。
このような傾向がある現場では、報告や相談は「気合い」や「タイミング」に頼ることになり、慣習化されません。
こうした問題を解決していくには、以下の対策が必要です。
プロジェクトの現場では、若手や新人が「これはおかしいかも?」と感じても、それを口に出せない空気が存在していることがあります。
そしてその沈黙が、小さなトラブルを放置し、やがて大きな炎上へとつながることも少なくありません。



まだ経験が浅いから、自分が間違っているのかもしれない。



自分が言うべきことじゃない気がする。



こんなことを言うと印象が悪い。
こうした思い込みは、本人の性格だけではなく、職位や年次によって発言のハードルが自然と高くなる構造によって生まれている側面もあります。
若手の発言対してに「ありがとう」や「よく気付いたね」といった感謝や肯定的なリアクションで返していくことや、ミーティングで若手が一言話す枠を設けることで、発言することを当たり前にしていくことで、ハードルをある程度下げていくことができます。
声が上がらない状況には、個人の問題ではなく、組織の構造や仕組みに原因がある場合が多く見られます。
報連相をタイミングに頼るのではなく、制度や文化の設計そのものを見直すことが、長期的には炎上を防ぐ土台になります。
この機会に、発言が自然に生まれるような構造的な改善を検討してみてはいかがでしょうか。
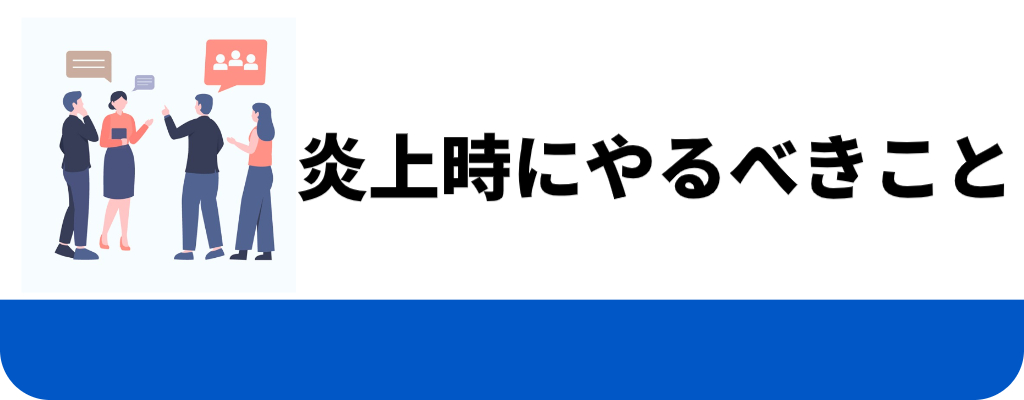
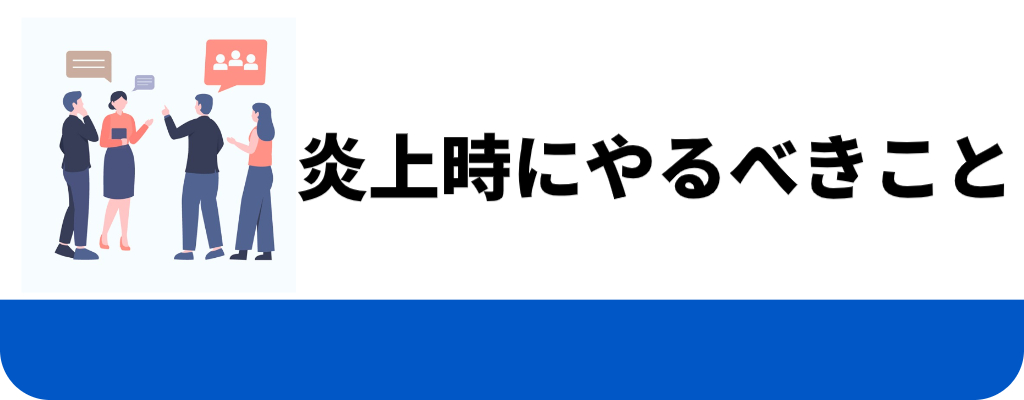
炎上してしまったプロジェクトにおいて、「冷静さ」と「順序立てた行動」が何よりも重要です。
場当たり的な対処を焦って繰り返すのではなく、冷静に状況を整理し、優先順位を立て、再構築することで炎上を収束することができます。
ここでは、炎上時の基本的な対応4ステップを具体的に紹介します。
炎上しているプロジェクトでは、現場が混乱しており、正確な全体像をつかめていないことが多くあります。
この状態で無理に進行しても、意味のない対処や優先順位のズレが発生し、かえって状況が悪くするリスクがあるため、まずは現状を正しく把握しましょう。
全体像を把握した後、プロジェクトを立て直すに、作業範囲を見直し、タスクの優先順位を決める必要があります。
納期やプロジェクトの中核になるものを確認し、「今やるべきこと」と「後回しにできること」を明確にし、優先順位をつけていきましょう。
プロジェクトが炎上している際には、現場だけで対応するのではなく、関係者の理解と支援を得る必要があります。
ここでは、現状と再構築の方針を関係者へ説明し、再スタートに対する合意と協力を得ていきます。
最後に、整理したタスクを並び替え、人員体制の見直しを行っていきます。
無理のない範囲で回していくことができるように仕切り直す必要があります。
プロジェクトがうまくいかない時こそ、冷静に状況を整理し、再構築していきましょう。
順序だてて対応していくことで、無理なく、現実的にプロジェクトを収束させることができます。
炎上は、個人の能力や一度のミスではなく、構造のゆがみや見過ごされたリスクの積み重ねで起きるものです。
状況を“誰かのせい”にするのではなく、仕組み・文化・設計の観点から見直す視点を持つことで、炎上を引き起こしづらい組織に近づくことができます。
システム開発・WEB制作案件の炎上でお困りの方は、お気軽にSELECTOまでご相談ください。
炎上を防ぐ方法の提案や、最適な制作会社選びをお手伝いします。